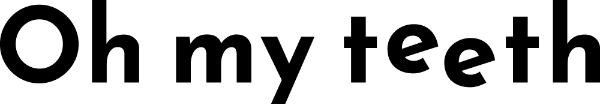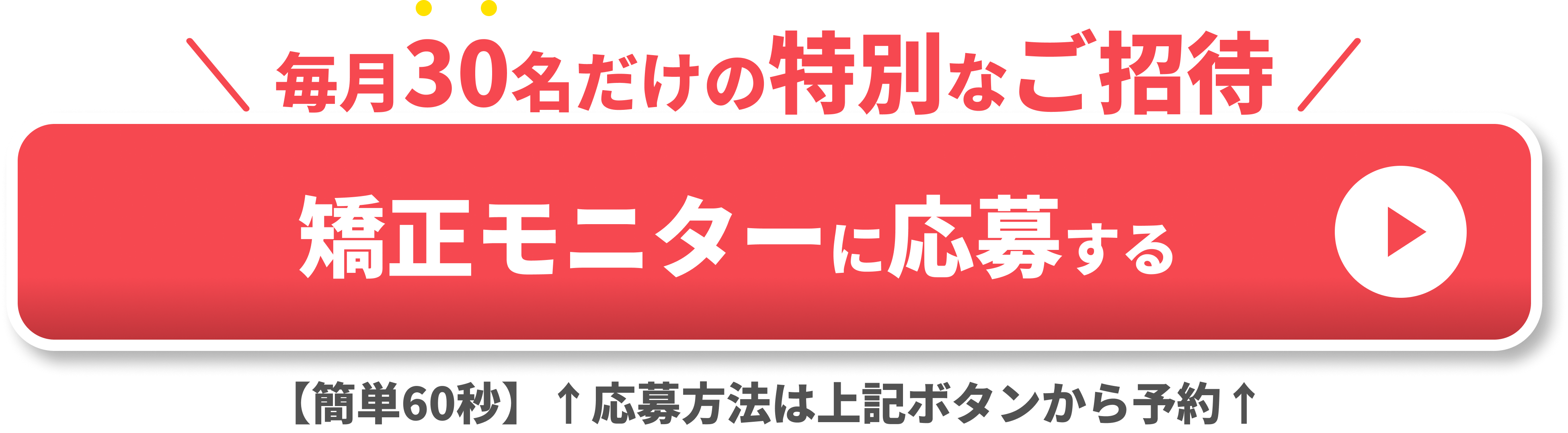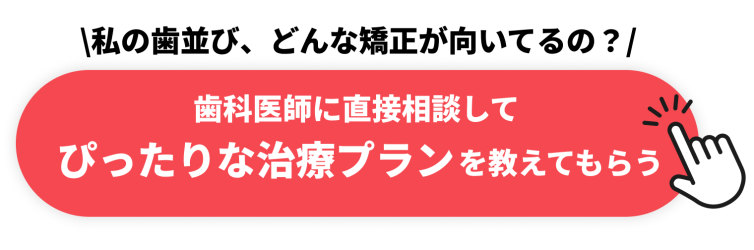歯科矯正
最終更新日:2025年6月30日
口呼吸は矯正できる?口呼吸の原因とリスク│鼻呼吸への矯正方法を解説

「口呼吸が癖になっているけど、大人になっても矯正できる?」
「子どもがいつも口を開けていて心配…」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
口呼吸は、口まわりの筋肉やあごの成長、歯並びにまで影響する重要な問題です。子どもだけでなく、大人でも放置すると口臭・歯周病・顔の印象の変化などにつながることがあります。
本記事では、口呼吸の原因や歯並びへの影響、鼻呼吸へ切り替える方法や相談先までをわかりやすく解説。市販グッズやトレーニング方法もご紹介します。
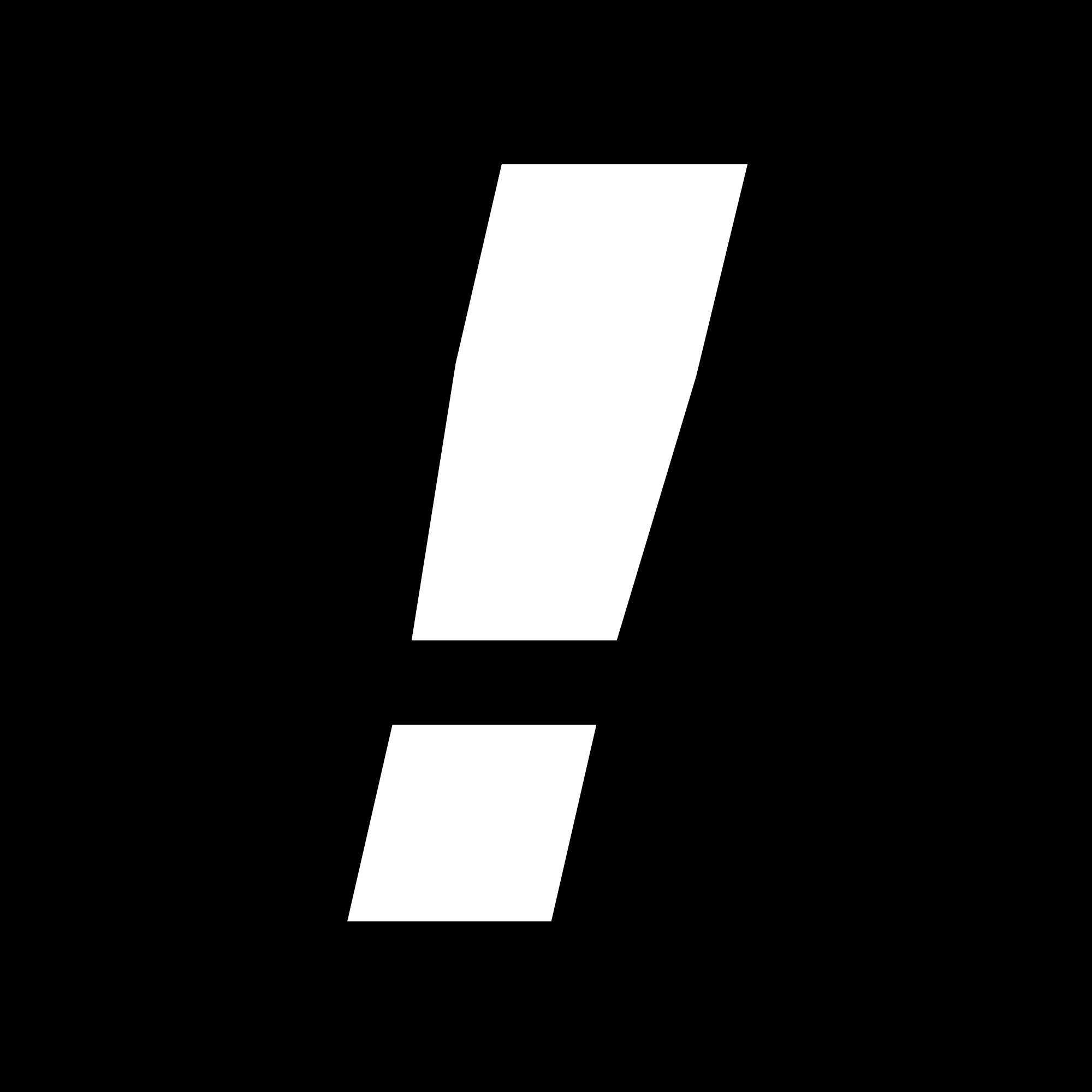
歯科矯正ブログ編集チーム
Oh my teeth
マウスピース矯正「Oh my teeth」ホームホワイトニング「Oh my teeth Whitening」を提供するOh my teethのコンテンツチームです。Oh my teeth導入クリニックのドクターと連携し、歯科矯正やホワイトニング、自社ブランドに関する確かな情報を発信しています。
目次
- 口呼吸かどうかをチェックする方法
- 口呼吸を矯正した方がいい理由は?口呼吸に潜む3つのリスク
- ①口まわりの筋肉のバランスが乱れる
- ②口ゴボにつながる
- ③虫歯や口臭のリスクが高まる
- 口呼吸を矯正するメリットは?
- 顔の印象が変わる
- 虫歯や口臭予防になる
- 風邪を引きにくくなる
- 発音がしっかりする
- 口呼吸になってしまう原因
- 鼻炎やアレルギー疾患
- アデノイド肥大
- 口まわりの筋力不足
- 歯並びの悪さ
- 口まわりの悪習慣
- 口呼吸の矯正方法
- ガムを噛む
- 舌をトレーニングする
- 口呼吸対策グッズを使う
- 歯科矯正治療を受ける
- 口呼吸の矯正はどこに相談したらいい?
- 歯科クリニック
- 耳鼻科や耳鼻咽喉科
- 口呼吸に関するよくある疑問(FAQ)
- 口を開けて寝るのを治す方法は?
- 口呼吸はどれくらいで治る?
- 子どもの口呼吸は何歳から矯正したほうがいい?
- 口呼吸の矯正は保険適用になる?
- 口呼吸が気になるなら早めに相談を
口呼吸かどうかをチェックする方法
「自分が口呼吸かどうかわからない」「子どもが寝ているとき、口が開いているけど大丈夫?」
そんな不安を感じたら、まずは簡単なセルフチェックをしてみましょう。
口呼吸セルフチェックリスト
✅️無意識のうちに口がぽかんと開いている
✅️朝起きたときに喉が痛いことが多い
✅️慢性的に鼻が詰まっている(アレルギー性鼻炎など)
✅️ 口臭が気になることがある
✅️ 就寝中よくいびきをかく
✅️ 風邪をひきやすい
✅️ 食事中にクチャクチャと音がする(咀嚼音が大きい)
✅️ 話していると唾が飛びやすい
上記の項目に当てはまる場合、口呼吸になっている可能性があります。
放置すると歯並びの悪化や虫歯・口臭のリスクが高まることもあるため、次のセクションで口呼吸のリスクをしっかり確認しましょう。
口呼吸を矯正した方がいい理由は?口呼吸に潜む3つのリスク

口呼吸はただの癖にとどまらず、身体や口元の健康、見た目などさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、口呼吸によって引き起こされるリスクを3つに分けて解説します。
「自分にも当てはまるかも」と感じた方は、早めの対策を検討してみてください。
①口まわりの筋肉のバランスが乱れる
口呼吸が続くと舌の位置が下がり、口まわりの筋肉のバランスが崩れて、歯並びが悪くなる原因になります。
本来、鼻呼吸をしているときの舌は、上あごのくぼみ(下のイラストの赤丸部分)にぴたりと収まるのが正しい状態です。

しかし、口呼吸が習慣化すると、口が開きやすくなり、舌は自然と下の方に落ちてしまいます。この状態は、舌の圧力よりも頬の圧力が優位になり、歯が内側に押されてしまいます。
結果として、出っ歯・乱ぐい歯(歯が並びきらず重なっている状態)・開咬(噛み合わせたときに上下の歯の間に隙間が開く状態)などにつながってしまうでしょう。
②口ゴボにつながる
口呼吸は「口ゴボ(口元の突出)」の原因のひとつです。口ゴボとは、口元全体が前に出ているように見える状態で、見た目の印象や顔のバランスに大きく影響します。
口ゴボの主な原因は、出っ歯や上下のあごのバランスの乱れ。口呼吸が続くことで口まわりの筋力バランスが崩れ、さらに指しゃぶりや頬杖などの悪習慣が重なると、上顎の過成長や下顎の発育不足を引き起こし、結果として口ゴボになりやすくなります。
以下のような特徴が当てはまる方は、口ゴボの傾向にあるかもしれません。
口ゴボセルフチェックリスト
✅️ 横から見ると、唇が鼻の高さと同じくらい前方に出ている
✅️ 口を閉じると人中(鼻の下)が長く見える
✅️ 横顔の輪郭がぼんやりしている(あごがないように見える)
✅️ 口を閉じるとあごに梅干しのようなシワができる
あわせて読みたい

口ゴボとは?セルフチェックの方法・原因・改善方法をわかりやすく解説
③虫歯や口臭のリスクが高まる
口呼吸は、虫歯や口臭のリスクを高める要因のひとつです。
通常、鼻呼吸をしていると口が閉じているため、唾液がしっかり分泌されて、歯や粘膜を洗い流す「自浄作用」が働いています。しかし、口呼吸では口が常に開いている状態になるため、口腔内が乾燥しやすくなり、唾液の働きが弱まってしまいます。
その結果、細菌が増殖しやすくなって、虫歯や口臭につながるのです。特に、朝起きたときに口のネバつきやのどの痛みを感じる方は、寝ている間に口呼吸をしている可能性があります。
口呼吸を矯正するメリットは?
口呼吸を鼻呼吸に切り替えると、見た目や健康面でさまざまなメリットがあります。
歯並びの乱れを予防するだけでなく、口臭や虫歯のリスクを減らしたり、体調を崩しにくくなったりと、日常生活にも良い変化が現れます。
【口呼吸から鼻呼吸に矯正するメリット】
- 顔の印象が変わる
- 虫歯や口臭予防になる
- 風邪を引きにくくなる
- 発音がしっかりする
顔の印象が変わる
口呼吸を鼻呼吸に変えると、口元が引き締まり、顔全体の印象がすっきりして見えることがあります。自然に口を閉じる習慣がつき、口まわりの筋肉がきちんと使えるようになるためです。
逆に口呼吸のままだと、口が開いた状態が続いて唇の力が弱くなり、歯並びや噛み合わせに悪影響が出てしまいます。その結果、顔のバランスが崩れて見えたり、口元がぼんやりした印象になることも。
「なんとなく顔がゆるんで見える…」そんな方は、まずは呼吸の習慣から見直してみるのもひとつの方法です。
虫歯や口臭予防になる
鼻呼吸が習慣になると、口の中がうるおいやすくなり、虫歯や口臭のリスクを抑えられます。唾液には、歯や粘膜を洗い流す自浄作用や細菌の繁殖を防ぐ働きがあり、口腔内の健康を保つうえで欠かせません。
口呼吸が続くと口の中が乾燥しやすく、唾液の働きが弱まり、細菌が繁殖しやすくなります。その結果、虫歯や歯周病、口臭の原因につながってしまうのです。
「歯磨きはしているのに口臭が気になる」という方は、呼吸の仕方が影響しているかもしれません。
風邪を引きにくくなる
鼻呼吸に切り替えると、空気中の細菌やウイルスの侵入を防ぎやすくなり、風邪を引きにくくなります。
鼻の中には、鼻毛や粘膜といったフィルターの役割を果たす仕組みがあり、ホコリ・花粉・病原菌などをブロックしてくれます。さらに、冷たく乾燥した空気も鼻を通ることで自然に温められ、適度な湿度が加わるため、喉や肺への刺激がやわらぎます。
一方、口呼吸ではこうしたフィルター機能が働かず、冷たく乾いた空気が直接気道に入り、体調を崩しやすくなることも。
「すぐに喉が痛くなる」「冬は風邪をひきやすい」と感じている方は、鼻呼吸を意識すると予防につながるでしょう。
発音がしっかりする
鼻呼吸を習慣にすると、舌の位置が安定しやすくなり、発音が明瞭になります。口呼吸が続くと、舌が本来あるべき位置から下がり(低位舌)、タ行やナ行など、舌を上あごにつけて発音する音が不明瞭になりやすくなります。
滑舌が悪く聞こえると感じる人は、舌の位置と呼吸のしかたが影響しているかもしれません。鼻から呼吸することで、自然と舌が正しい位置に収まりやすくなり、発音がはっきりするケースもあります。
口呼吸になってしまう原因
口呼吸は、癖ではなくさまざまな身体的・習慣的な原因によって起こります。
まずは、考えられる主な原因を確認してみましょう。
まずは、考えられる主な原因を確認してみましょう。
【口呼吸の原因】
- 鼻炎やアレルギー性鼻炎による鼻づまり
- アデノイド(咽頭扁桃)の肥大
- 舌や口まわりの筋力低下
- 歯並びの悪さ
- 指しゃぶりや頬杖などの悪習慣
ここからは、それぞれの原因について詳しく解説していきます。
鼻炎やアレルギー疾患
慢性的な鼻づまりだと、口呼吸が習慣になりやすくなります。アレルギー性鼻炎や花粉症、副鼻腔炎などで鼻が常に詰まっている状態では、無意識のうちに口で呼吸するしかなくなるためです。
治療によって鼻の通りが改善されていれば問題ありませんが、症状が続いている場合は、どれだけ意識しても鼻呼吸をするのが難しいこともあります。この場合は、呼吸習慣を変える前に、耳鼻科での疾患の治療が先決です。
アデノイド肥大
アデノイドが大きくなると鼻の通りが悪くなり、口呼吸の原因になります。
アデノイドとは、鼻の奥(上咽頭)にあるリンパ組織の一種です。2歳ごろから徐々に大きくなり、6歳前後でピークに達し、その後10歳ごろには自然に小さくなるとされています。
しかし、アデノイドが肥大した状態が続くと、次のような症状を引き起こすことがあります。
- 口呼吸
- 無意識に口をぽかんと開けてしまう
- 鼻づまり
- 睡眠中のいびきや無呼吸
お子さんがいつも口を開けていたり、夜によくいびきをかいていたりする場合は、一度耳鼻科でアデノイドの状態を確認してもらうと安心です。
口まわりの筋力不足
口のまわりの筋肉が弱いと、自然に口を閉じることができず、口呼吸になりやすくなります。
特に「口輪筋」と呼ばれる筋肉が衰えると、意識していないと口がぽかんと開いてしまう状態に。
口まわりの筋力の低下は、やわらかいものばかりであまり噛まなくてもいい食生活が原因として考えられます。最近では、スマホを見ながら食べる習慣によって、口の動きが減っているケースも少なくありません。
日頃の食習慣を見直すことも、口呼吸を防ぐための大切なポイントです。
歯並びの悪さ
歯並びが乱れていると、口呼吸を引き起こす原因になります。例えば、出っ歯(上顎前突)や口ゴボと呼ばれる状態では、唇がきちんと閉じられず、常に口が開いたままになりがちです。
その結果、無意識のうちに口呼吸する習慣がついてしまい、さらに口まわりの筋肉が使われにくくなるという悪循環に陥ることもあります。
歯並びと呼吸は密接に関係しているため、「口が閉じにくい」「口元が出ている」と感じている場合は、歯科クリニックでの相談も検討しましょう。
口まわりの悪習慣
日常のちょっとした癖も、口呼吸を引き起こす原因です。
頬杖をつく、うつ伏せで寝る、口を開けたままテレビを見るなどの癖は、あごの形をゆがめ、口が閉じにくくなることがあります。舌で前歯を押す・指しゃぶりをするなどの癖も、出っ歯や噛み合わせの乱れにつながり、結果的に口呼吸を誘発する要因にもなります。
特に成長途中の子どもは、あごや骨格がやわらかく、姿勢や習慣の影響を受けやすいため注意が必要です。「癖だから大丈夫」と放置せず、日頃の行動を見直すことが、口呼吸の予防につながります。
口呼吸の矯正方法

口呼吸を改善するには、生活習慣の見直しや筋力トレーニング、歯科矯正など、さまざまな方法があります。
【口呼吸の矯正方法】
- ガムを噛む
- 舌をトレーニングする
- 口呼吸対策グッズを使う
- 歯科矯正治療を受ける
「自分や子どもが口をぽかんと開けていることが多い」「寝ているときに口が開いている」など気になる場合は、できる対策から始めてみましょう。
ガムを噛む
ガムを噛むことで口まわりの筋肉が鍛えられ、口を閉じる力がつきやすくなります。
口のまわりの筋力(口輪筋)の低下は口呼吸の原因のひとつ。ガムを噛む動作は、この筋肉にほどよい刺激を与えるトレーニングになります。
効果を高めるには、ただ噛むだけでなく、少し大げさなくらいしっかりと口を動かすことがポイントです。
日常生活の中で手軽に取り入れられる方法なので、まずここから試してみるのもおすすめです。
舌をトレーニングする
舌の位置が整うと、鼻呼吸への切り替えがしやすくなります。効果的なのが、舌と口まわりの筋肉を同時に鍛えられる「あいうべ体操」です。
この体操は、「あ」「い」「う」と大きく口を動かし、最後に「べ」で舌を思い切り下に出すというシンプルな動作です。1セット4動作で、食後に10セットずつ、1日3回(計30セット)を目安に続けてみてください。
1か月ほど継続することで、舌の筋力がつきやすくなり、自然と舌が正しい位置に収まりやすくなります。お子さまから大人まで気軽に取り組めるので、口呼吸が気になる方におすすめのトレーニングです。
口呼吸対策グッズを使う
口を閉じる習慣づけとして、口呼吸対策用のテープやマスクなどを活用するのもひとつの方法です。寝ているあいだに無意識に口が開いてしまう方には、就寝時に使える専用アイテムが市販されています。
ただし、使用には注意が必要です。特に小さなお子さんの場合、呼吸の妨げになるリスクがあるため、使用前に医師に相談するのが安心です。
グッズに頼りすぎず、筋力不足や鼻づまりなど根本的な原因への対処と併用することが大切です。
歯科矯正治療を受ける
歯並びが原因で口が閉じにくい場合は、歯科矯正によって口呼吸の改善が期待できます。
出っ歯や噛み合わせの問題があると、どれだけ意識しても口が開いてしまい、呼吸の癖もなかなか直りません。「筋トレや対策グッズを試しても改善しない」「そもそも口が閉じにくい」と感じる方は、歯並びを整えることが近道になることもあります。
Oh my teethの無料診断では専門の歯科医師が、一人ひとりの口元に合った矯正プランを提案しています。口呼吸を根本から改善するためにも、まずはプロに相談してみましょう。
口呼吸の矯正はどこに相談したらいい?

「自分で口呼吸を改善しようとしてもなかなか変わらない……」という場合は、専門の医療機関に相談するのが確実です。
口呼吸の原因は人によって異なり、歯並びの乱れ、鼻づまり、筋力低下など複数の要素が関係していることもあります。
そのため、自己判断で対策を続けるよりも、症状に応じたクリニックを受診することで、より効果的な改善が期待できます。
歯科クリニック
口呼吸と同時に歯並びも気になっている場合は、歯科クリニックを受診して相談してみましょう。特に矯正歯科では、歯並びだけでなく、口まわりの筋力や呼吸の癖まで含めて総合的に診てもらえることが多いです。
小児矯正では、MFT(口腔筋機能療法)と呼ばれるトレーニングを行うことで、筋力バランスや口呼吸の習慣が改善され、矯正装置を使わずに歯並びが整うケースもあります。
大人の場合でも、矯正治療と並行して呼吸習慣を見直すことで、口呼吸と歯並びの改善を目指せます。
耳鼻科や耳鼻咽喉科
鼻づまりやアレルギーといった不調がある場合は、耳鼻科や耳鼻咽喉科での診察がおすすめです。
慢性的な鼻炎や副鼻腔炎、花粉症などが原因で口呼吸になっているケースでは、根本的な原因を治療することで、自然と鼻呼吸へと改善する可能性があります。
子どもに多いアデノイド肥大が疑われる場合も、耳鼻科で適切な検査と判断を受けることが大切です。
口呼吸に関するよくある疑問(FAQ)
ここでは、口呼吸に関して多くの方が疑問に思うポイントをQ&A形式でまとめました。
「治るまでどれくらいかかるの?」「寝ているときの対策は?」といったよくある質問にわかりやすくお答えします。
口を開けて寝るのを治す方法は?
まずは、加湿や鼻洗浄などで鼻の通りをよくし、呼吸がしやすい環境を整えましょう。
それでも改善が難しい場合は、就寝時に口を閉じるための専用テープやマスクを活用する方法もあります。
ただし、子どもや鼻づまりが強い方が口呼吸対策グッズを使う場合は、呼吸の妨げにならないよう十分に注意が必要です。不安があるときは、事前に医師に相談してから使用を検討してくださいね。
また、枕の高さが高すぎる・低すぎる場合も口が開いた状態になります。口を開けて寝るのを治すためには、専門店などで相談しながら、自分の体型に合った枕を選ぶのがおすすめです。
口呼吸はどれくらいで治る?
原因や年齢によって異なりますが、早い人で数週間、長いと数か月以上かかることもあります。
単なる癖が原因であれば、意識づけやトレーニングによって比較的早期に改善できるケースがあります。一方で、歯並びの問題や慢性的な鼻づまりが関係している場合は、歯科矯正や治療が必要になり、ある程度の時間がかかることも。
いずれにしても、自己判断せず、専門家に相談して原因をはっきりさせることが改善への近道です。
子どもの口呼吸は何歳から矯正したほうがいい?
3〜5歳ごろからのアプローチが効果的とされています。この時期はあごや口まわりの筋肉が発達する大切な時期であり、癖づけや筋力トレーニングによる改善が期待できます。
特に「ぽかん口」や「いびきがある」「指しゃぶりが続いている」などの兆候が見られる場合は、早めの対策が重要です。MFT(口腔筋機能療法)などのトレーニングで、筋力を整えるだけでも呼吸の習慣が変わることがあります。
口呼吸の矯正は保険適用になる?
原則として、口呼吸そのものの矯正は保険適用外です。
ただし、鼻炎やアデノイド肥大などの治療が必要と判断された場合は、耳鼻科での診察・治療に保険が適用されることがあります。
歯並びの改善を目的とした矯正治療も基本的に自由診療(自費)ですが、顎変形症などの特定の疾患がある場合に限り、保険が適用されるケースもあります。
気になる方は、事前に医療機関で相談し、保険が適用されるかどうか確認しておきましょう。
口呼吸が気になるなら早めに相談を

口呼吸はそのままにすると、歯並びや顔つき、体調にまで影響を及ぼすことがあります。
子どもの場合はあごの成長や骨格形成に、大人の場合も筋力低下や歯周病・口臭リスクの増加など、さまざまな不調の引き金になることがあります。
「いつの間にか口が開いている」「人から口呼吸を指摘された」そんな小さな気づきが、見直しのきっかけに。年齢を問わず、早い段階で専門家に相談することで、より自然な改善が期待できます。
Oh my teethの無料診断では、矯正専門の歯科医師が口元のお悩みに合わせた矯正プランをご提案。「口呼吸は歯並びの影響かも?」と気になったら、まずはお気軽にご相談ください。