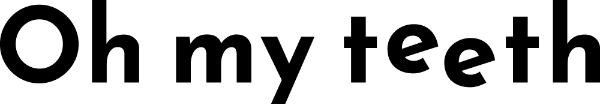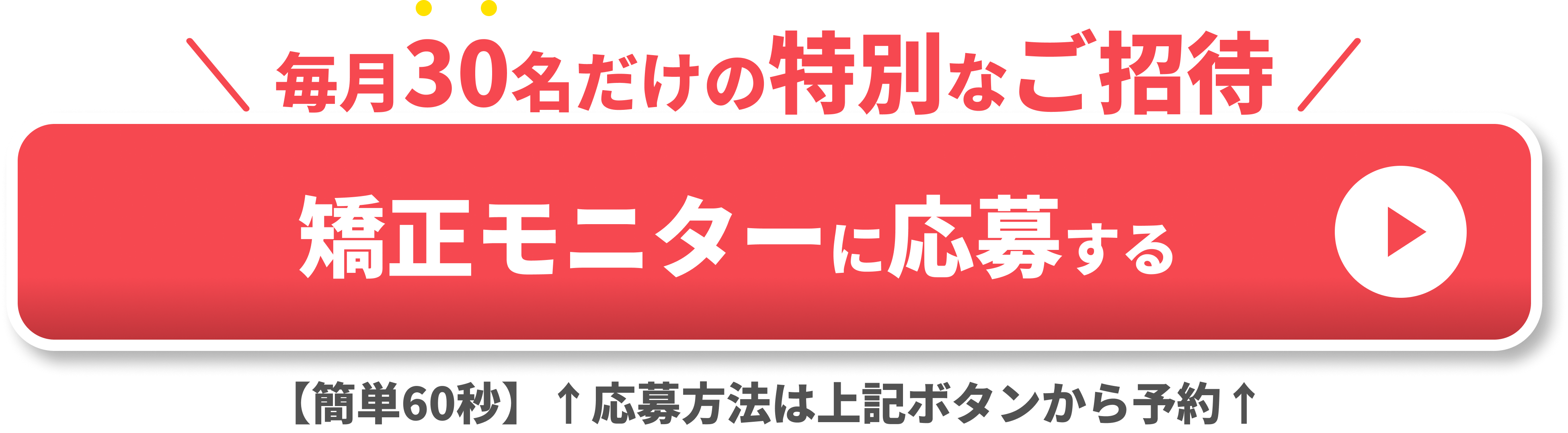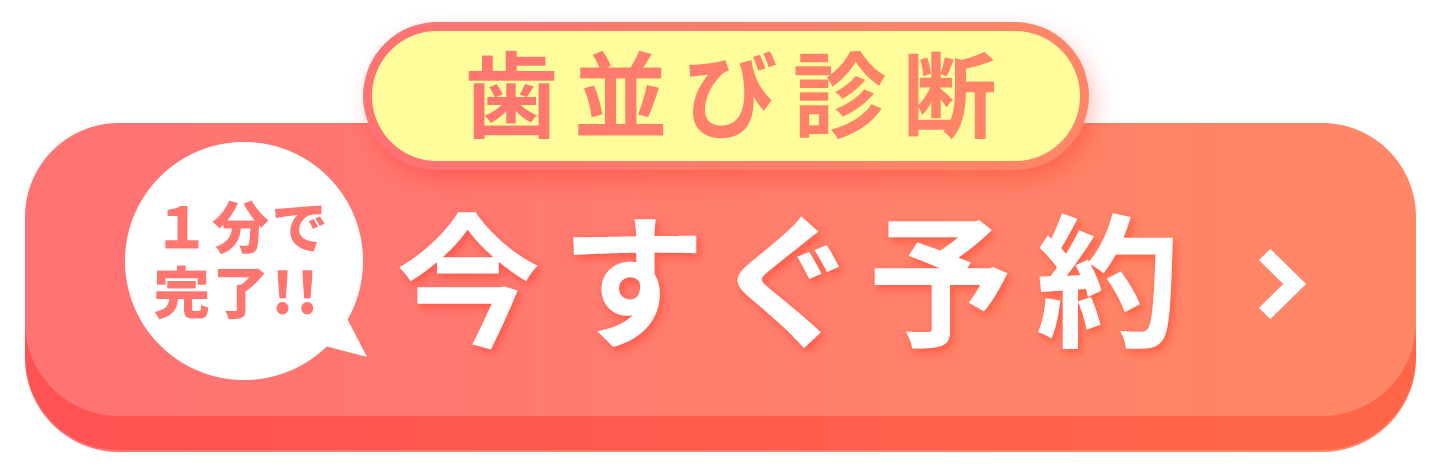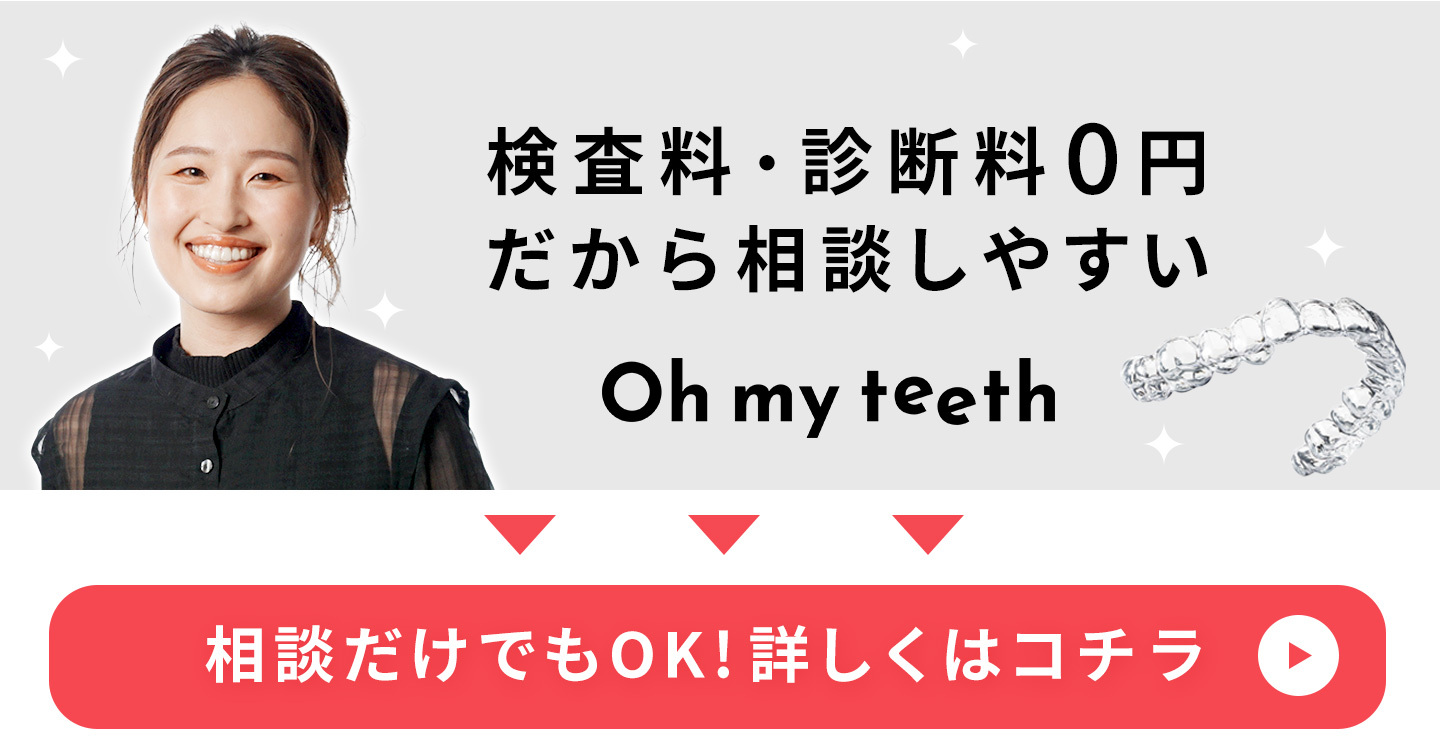歯科矯正
最終更新日:2025年6月27日
子どもの歯科矯正は何歳から?症例別の始めどき・治療内容・費用まとめ

「子どもの歯科矯正は何歳から?」
「小児矯正を今からはじめるのは遅すぎ?」
「小児矯正を今からはじめるのは遅すぎ?」
このようにお悩みの方に向けて、本記事では子どもの歯科矯正の開始時期や、小児矯正で使用される装置や治療にかかる料金の目安を解説します。
この記事があなたのお子様の美しい歯並びづくりの手助けになれば幸いです。

目次
- 子どもの歯科矯正は何歳から始めるべき?
- 不安がある場合は早めの相談が安心
- 小児矯正をはじめるタイミングは大きく3つ
- 小児矯正(0期および1期治療)で行われる内容
- 取り外し可能な装置(口の中に装着)
- 取り外し可能な装置(口の外に装着)
- 取り外し不可の装置
- 子どもの歯科矯正(2期治療)で行われる内容
- ワイヤー矯正
- マウスピース矯正
- コンビネーション矯正
- インプラント矯正
- 子どものころから歯科矯正を始めるメリット
- あごの発育を生かせる
- 口まわりの悪習慣を改善できる
- 2期治療時の抜歯を防げる
- 子どもへの負担を減らせる
- 小児矯正のデメリット
- 治療期間が長くなる傾向がある
- 自己コントロールが難しい
- むし歯リスクが高まる
- 早めに歯科矯正を始めたほうがいい症例
- 受け口
- 前歯が噛み合わない
- 出っ歯
- 噛み合わせが深い
- 一部の噛み合わせが逆
- 【歯並び別】歯科矯正スタートにおすすめの年齢
- 受け口:4歳から5歳ごろ
- 出っ歯:8歳から10歳ごろ
- ガタガタの歯:奥歯の噛み合わせ次第
- 小児矯正にかかる料金・期間
- 保定期間も必要
- 2期治療を割引してくれる場合も
- 子どもの歯並びの不安は早めに相談を
Oh my teethのマウスピース矯正は子供でもできる?
マウスピース矯正 Oh my teethは、以下の条件を満たされた15歳以上の方を対象しています。
- 全ての歯が永久歯に生え変わっていること。
- 上下顎の臼歯(7番)が生えていて、咬合していること。
- 直近一年で伸びた伸長が3センチ以下であること。
未成年の場合は親権者の同意が必要です。
Oh my teethでは高校生活中に矯正を終えられたユーザーもいます。通院は原則不要なので学校生活に影響を与えることなく矯正治療を受けられます。
Oh my teethでは高校生活中に矯正を終えられたユーザーもいます。通院は原則不要なので学校生活に影響を与えることなく矯正治療を受けられます。
子どもの歯科矯正は何歳から始めるべき?

「子どもの歯科矯正は何歳からはじめるべきか?」
この答えは、お子様のあごや歯の状態によって異なります。
しかし1つの目安としては「小学1年生」ごろから小児矯正をスタートするのがおすすめです。
この理由としては、
- 小学1年生くらいの年齢になると、歯科クリニックの診察台で、一定時間治療を受けられるようになる
- 小学1年生はあごの成長過程にあるため、この時期に矯正をスタートすることで矯正装置を使わずに歯をきれいに並べられる可能性がある
といった点が挙げられます。
不安がある場合は早めの相談が安心
「歯科矯正のスタートは小学1年生がおすすめ」というのは、あくまでも目安です。
特に口まわりの悪習慣(口呼吸・指しゃぶり・舌を突き出す・頬杖をつく・爪を噛む など)があり、歯並びに不安がある場合、小学校入学より前に、歯科クリニックに相談することをおすすめします。
なぜなら早めに歯科クリニックに相談することで、口まわりの悪習慣が原因で起こる歯並びの悪化を防ぎ、健やかなあごの発育を促せるからです。
次の項目からは、一般的な小児矯正のタイミングを紹介します。
それぞれの時期に合った矯正方法があるため、お子様の歯並びや口まわりの習慣が気になる場合は、早めにかかりつけの歯科クリニックなどに相談してみましょう。
小児矯正をはじめるタイミングは大きく3つ
子どもの歯科矯正のタイミングは、大きく以下3つあります。
以下は、子どもの歯科矯正のタイミングと、それぞれの治療を行う年齢(目安)や、用いられる装置の例をまとめた表です。
治療を行う年齢(目安) | 治療の目的・内容 | 用いられる装置の例 | |
|---|---|---|---|
0期治療 | 3歳〜5歳頃 | ・乳歯の時期の行う ・噛み合わせによるあごのズレを改善する ・歯並びに悪影響を及ぼす悪習慣を早めに治す(口腔筋機能療法「MFT」) | ・ムーシールド ・プレオルソ |
1期治療 | 6歳〜12歳頃 | ・乳歯と永久歯が混在する時期に行う ・受け口・出っ歯の矯正治療はこのタイミングで行うことが多い ・あごが小さすぎてはが並び切らないと判断された場合、あごの発育を促す装置を用いる | ・リンガルアーチ ・ヘッドギア ・T4K ・拡大床 ・リップバンパー ・バイオネーター ・マウスピース型矯正装置 |
2期治療 | 13歳以降 | ・永久歯が生え揃った後に行う ・基本的に大人の矯正治療を同じ内容 | ・マルチブラケット装置 ・マウスピース型矯正装置 ・歯科矯正用アンカースクリュー |
このように、子供の歯科矯正は
- 0期治療:3〜5歳ごろ
- 1期治療:6〜12歳ごろ
- 2期治療:13歳以降
の3つのタイミングに分かれます。
以上のタイミングのうち、子どもの時期ならではの治療を行えるのは、基本的に0期治療と1期治療。2期治療で行う内容は、基本的に大人になってからの歯科矯正と同様です。
次の項目からはより具体的に、それぞれのタイミングで行う歯科矯正の内容を見ていきましょう。
小児矯正(0期および1期治療)で行われる内容

子どもの歯科矯正のうち、0期治療と1期治療では、あごの発達途中であることを生かした治療が行われます。
また、乳歯から永久歯の生え変わりの時期に指しゃぶりや舌の使い方の悪さなどがあると、歯並びが悪化する原因に。
そのため0期および1期治療では、口まわりの悪習慣を取り除いたり、舌や口まわりの筋肉の使い方を改善したりする治療方法が適応されることもあります。
以下は0期治療および1期治療で用いられる矯正装置の例と、適応症例や装着時間(目安)についてまとめた表です。
口の中に装着するもの・口の外に装着するもの・取り外し不可もの、それぞれでまとめましたので、参考にしてくださいね。
取り外し可能な装置(口の中に装着)
装置の種類 | 特徴 | 適応症例 | 装着時間 |
|---|---|---|---|
拡大装置(拡大床・エクスパンションプレート) | ・あごを広げて歯が並ぶスペースを作る ・中心のネジを調整いsて拡大床(プレート)のハガをゆっくり広げあごを押し広げる | ・ガタガタの歯並び ・八重歯 | 12時間〜15時間/日 |
T4K | 舌を突き出す癖や口呼吸などの習慣を改善し、あごの成長をサポートする | ・ガタガタの歯並び ・受け口 ・深い噛み合わせ(過蓋咬合) | 日中1時間〜2時間+就寝中 |
マイオブレース | 舌を突き出す癖や口呼吸などの習慣を改善し、あごの成長をサポートする | ・ガタガタの歯並び ・受け口 ・深い噛み合わせ(過蓋咬合) | 日中1時間〜2時間+就寝中 |
ムーシールド | 舌や口周りの筋肉の状態を整え受け口改善をサポートする | 受け口 | 就寝中 |
プレオルソ | 舌を突き出す癖や口呼吸などの習慣を改善し、あごの成長をサポートする | ・出っ歯 ・受け口 ・ガタガタの歯並び | 日中1時間〜2時間+就寝中 |
インビザライン ファースト | 乳歯と永久歯が混在する時期用のマウスピース型矯正装置 | 広範囲にわたる噛み合わせや歯並びの悪さ | 20時間以上/日 |
バイオネーター | 筋肉の動きを生かして下あごの成長をサポートする | 深い噛み合わせ(過蓋咬合) | 10時間以上/日 |
リップバンパー | 唇の圧力を抑え歯並びの悪化を防ぐ | 受け口 | 18時間以上/日 |
拡大装置(拡大床・エクスパンションプレート)
あごを広げて歯が並ぶスペースを作る装置です。中心のネジを調整して拡大床(プレート)の歯がをゆっくり広げ、あごを押し広げます。
主な適応症例はガタガタの歯並びや八重歯。装着時間の目安は12時間〜15時間/日です。
以下の記事では、拡大床について詳しく解説しています。拡大床のメリットやデメリットも紹介していますので参考にしてください。
あわせて読みたい

拡大床の使い方や種類・メリット・デメリットを解説
T4K・マイオブレース
舌を突き出す癖や口呼吸などの習慣を改善し、あごの成長をサポートする装置です。
主な適応症例はガタガタの歯並び・受け口・深い噛み合わせ。日中1時間〜2時間と就寝中に装着します。
ムーシールド
受け口の治療で用いられる装置。舌や口周りの筋肉の状態を整え、受け口改善をサポートします。就寝中に装着します。
プレオルソ
舌を突き出す癖や口呼吸などの習慣を改善し、あごの成長をサポートする装置です。
主な適応症例はガタガタの歯並び・受け口・出っ歯。日中1時間〜2時間と就寝中に装着します。
インビザライン ファースト
乳歯と永久歯が混在する時期用のマウスピース型矯正装置。広範囲にわたる噛み合わせや歯並びの悪さに対応できます。
成人矯正で用いられるマウスピース型矯正装置同様、1日20時間以上の装着が必要です。
バイオネーター
筋肉の動きを生かして下あごの成長をサポートする装置。出っ歯・受け口・深い噛み合わせの治療に用いられます。装着時間は1日10時間以上です。
リップバンパー
唇の圧力を抑え歯並びの悪化を防ぐ装置。
主に下あごの小児矯正(下の前歯の後方への傾きを防ぐ・奥歯の移動を防ぐ・永久歯が生えてくるスペースを確保する など)に用いられます。装着時間は1日18時間以上です。
取り外し可能な装置(口の外に装着)
装置の種類 | 特徴 | 適応症例 | 装着時間 |
|---|---|---|---|
フェイシャルマスク | 上あごを前方へ引っ張り前方への成長をサポートする | 受け口 | 12時間以上/日 |
ヘッドギア | 上あごの成長を抑える | 出っ歯 | 17時間以上/日 |
フェイシャルマスク
受け口の改善に用いられる装置。上あごを前方へ引っ張り、前方への成長をサポートします。装着時間は1日12時間以上です。
ヘッドギア
上あごの成長を抑える目的で使われる装置。出っ歯の改善に用いられ、装着時間は1日17時間以上です。
取り外し不可の装置
装置の種類 | 特徴 | 適応症例 |
|---|---|---|
リンガルアーチ | 抜歯をともなう矯正を行う際、臼歯(後方にある歯)が前方に移動するのを防ぐ | 受け口 |
トランスパラタルアーチ | 抜歯をともなう矯正を行う際、臼歯(後方にある歯)が前方に移動するのを防ぐ | 受け口 |
急速拡大装置 | 固定式の拡大装置 中心のネジを回してあごを押し広げる | ガタガタの歯並び |
クワドヘリックス | 固定式の拡大装置 バネの力でゆっくりあごを押し広げる | ガタガタの歯並び |
タングガード | 舌が前方に移動するのを防ぎ、歯並びの悪化を防ぐ | 前歯が噛み合わない(開咬) |
ツーバイフォー(2×4) | 奥歯2本を固定源にし、前歯4本を動かす | 凸凹の歯並び 受け口 出っ歯 |
リンガルアーチ
抜歯をともなう矯正を行う際、臼歯が前方に移動するのを防ぐ装置です。主な適応症例は前歯部分の反対咬合やデコボコ歯です。
トランスパラタルアーチ(TPA)
抜歯をともなう矯正を行う際、臼歯が前方に移動するのを防ぐ装置です。主な適応症例は受け口です。
急速拡大装置
固定式の拡大装置です。中心のネジを回してあごを押し広げます。
主な適応症例はガタガタの歯並びです。
クワドヘリックス
固定式の拡大装置です。バネの力でゆっくりあごを押し広げます。
主な適応症例はガタガタの歯並びです。
タングガード
舌が前方に移動するのを防ぐ装置です。前歯が噛み合わない場合に用いられます。
ツーバイフォー(2×4)
奥歯2本を固定源に、前歯4本を動かす装置です。主な適応症例はデコボコ歯・受け口・出っ歯。
このように、子どもの歯科矯正(0期治療・1期治療)で用いられる矯正にはさまざまなものがあります。
特に取り外しが可能かどうかは、お子様の生活スタイルや特性に合わせて選ぶべきでしょう。
子どもの歯科矯正(2期治療)で行われる内容
子どもの歯科矯正の2期治療で行われる内容は、基本的に大人の矯正と同様です。
装置の種類 | 特徴 |
|---|---|
ワイヤー矯正 | ブラケットという装置を歯につけ、そこへワイヤーを通し、適切な力をかけて歯を少しずつ移動させる 装置をつける場所によって「表側矯正」「裏側矯正(舌側矯正・リンガル矯正)」「ハーフリンガル矯正」の3種類ある |
マウスピース矯正 | 矯正用の透明なマウスピースを装着して歯を少しずつ移動させる 1〜2週間ごとにマウスピースを交換しながら矯正を進める |
コンビネーション矯正 | 一般的に矯正治療期間の前半にワイヤー矯正、後半にマウスピース矯正を行う |
インプラント矯正 | アンカースクリューと呼ばれる小さなチタン製のネジを歯茎に埋め込み、そこを支点にして歯を動かす 他の矯正方法と並行する |
ワイヤー矯正
ブラケットという装置を歯につけ、そこへワイヤーをとおし、適切な力をかけて歯を少しずつ移動させます。
装置をつける場所によって、表側矯正・裏側矯正・ハーフリンガル矯正の3つに分かれます。
マウスピース矯正
矯正用の透明なマウスピースを装着して歯を少しずつ移動させます。1〜2週間ごとにマウスピースを交換しながら矯正を進めます。
コンビネーション矯正
一般的に前半にワイヤー矯正、後半にマウスピース矯正を行います。
インプラント矯正
アンカースクリューと呼ばれる小さなチタン製のネジを歯茎に埋め込み、そこを支点にして歯を動かします。ほかの矯正方法を並行されます。
このような2期治療は、0期および1期治療であごの発達が十分に促せれば、不要になることもあります。
あるいは0期および1期治療で歯がきれいに並ばなくても、2期治療での抜歯が不要になるケースもあります。
2期治療から矯正治療を始めるなら、 マウスピース矯正 Oh my teethを検討してみませんか?初回検査を受けた後、マウスピースがご自宅に届けられ、原則として通院する必要がありません。
週に1度、マウスピースを装着した状態の写真をLINEで送信し、その写真をもとにドクターが治療の進行状況を確認して進めます。
部活動や習い事、アルバイトなどで忙しい生活を送る学生さんも効率的に矯正治療を受けられますよ。
※歯並びの状態によっては複数回の通院が必要
子どものころから歯科矯正を始めるメリット
子どものころから歯科矯正を始める最も大きなメリットは、大人の矯正とは異なり、あごの発育を生かした治療ができる点です。
あごの発育を生かせる
そもそも歯並びが悪化する原因は、大きく以下の2つに分けられます。
- あごの問題:あごが小さすぎる・あごの発育不良(上あごあるいは下あごが成長し過ぎている)
- 歯の問題:歯が大きすぎる・歯が小さすぎる・歯の数が多い
子どものころから歯科矯正を始めると、上記のうちのあごの問題にアプローチできるメリットがあります。
あごの発育は15歳ごろまでにほぼ完了するといわれています。小児矯正では、このあごの発達過程でアプローチすることで、あごの成長を生かした矯正が可能に。
その結果、本格的な矯正装置を使わずに歯をきれいに並べられる可能性も高まります。
口まわりの悪習慣を改善できる
歯並びが悪化する原因の中には、口まわりの悪習慣も含まれます。たとえば以下のような習慣が、歯並びに悪影響を与えるといわれています。
【歯並びに悪影響を及ぼす癖】
- 口呼吸
- 指しゃぶり
- 舌を突き出す
- 爪を噛む
- 頬杖をつく
このような悪習慣を放置すると、子どものあごの健やかな発達が妨げられ、スムーズな食事や発語ができなくなるリスクさえあります。そのため早めのアプローチが重要です。
口呼吸が歯並びに与える影響についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しています。
あわせて読みたい

口呼吸は矯正できる?口呼吸の原因とリスク│鼻呼吸への矯正方法を解説
2期治療時の抜歯を防げる
0期治療や1期治療であごの矯正を行えると、たとえそれだけでは歯がきれいに並ばなくても、2期治療がスムーズにできる土台が整えられます。
2期治療から矯正をスタートすると、抜歯が必要になることも多いです。
しかし0期治療や1期治療で健やかなあごの発達を促せたことで、歯がきれいに並ぶスペースを確保でき、抜歯を避けられる可能性も。また、結果的に2期治療の期間を短縮できるメリットもあります。
子どもへの負担を減らせる
0期治療や1期治療で用いられる装置は、基本的に就寝中の装着でOKだったり、日中も1から2時間程度の装着でOKだったりするものがあります。
この場合、保育園や幼稚園、小学校などには装着していかなくてもよいため、子どもへの負担も軽く済むでしょう。
また、取り外し不可の装置であっても、2期治療で装着するブラケットやワイヤーよりも目立ちにくいものもあります。
0期治療と1期治療であごの発達が十分に促せれば、2期治療を行わなくても歯がきれいに並んだり、抜歯が不要になったりすることも。
結果的に子どもへの精神的・身体的負担を軽減できるでしょう。
小児矯正のデメリット

子どものころから歯科矯正を始めると、治療期間が長引きやすいなどのデメリットもあります。
治療期間が長くなる傾向がある
たとえば0期から矯正治療をスタートし、2期治療まで行ったとすると、3歳ごろから18歳ごろまで歯科矯正を続けることになります。
また歯科矯正治療完了後は保定期間(歯科矯正で動かした歯が元通りになるのを防ぐ期間)も必要。
保定期間は一般的に、矯正を行った同じ期間必要とされています。
そのため、たとえば歯科矯正治療に3年かかったとしたら、さらに3年は保定装置(リテーナー)を装着するのが理想的です。
自己コントロールが難しい
0期治療や1期治療で行われる方法は、子ども自身の頑張りによって効果に差が出やすいです。
特に着脱可能な装置を使用する場合、子どもが装着を嫌がれば、装着目安となる時間を確保するのが難しくなります。その結果、当初の計画通りにあごの発達が見込めないリスクも。
小児矯正では、子どもをサポートするまわりの家族の努力も必要になることを念頭に入れておきましょう。
むし歯リスクが高まる
小児矯正で用いられる装置の中には、着脱可能なものもあります。この場合、ブラッシングの際には外すことができるため、口腔内を清潔に保ちやすいでしょう。
一方で着脱不可な装置を用いる場合、ブラッシングがしにくいです。親御さんが仕上げ磨きをするなど、まわりの家族のサポートが重要になります。
早めに歯科矯正を始めたほうがいい症例

子どものうちから歯科矯正を始めたほうがいいかどうかは、お子さんの歯やあごの状態によって異なります。
しかし以下のような場合、早期に歯科クリニックに相談したほうがいいでしょう。
受け口
受け口は専門的には「反対咬合(はんたいこうごう)」と呼ばれる状態。早期に歯科矯正を始めたほうがいいとされる代表的な症例です。
受け口は発語・食事に悪影響を与え、放置していると上あごの成長を妨げたり、歯へのダメージが蓄積されたりしてしまいます。
前歯が噛み合わない
前歯が噛み合わない状態は「開咬(かいこう)」といいます。これは奥歯が噛み合った状態で、前歯が噛み合わない状態のことを指します。
前歯が噛み合わないと、発語する際に息が漏れやすくなり、会話の妨げになるリスクが。
前歯が噛み合わなくなる原因としては、口呼吸や舌を押し出す癖などが挙げられます。このような悪い習慣は、早期に改善する必要があります。
出っ歯
出っ歯は専門用語では「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」といい、指しゃぶりが原因になっていることがあります。
この場合、早期に指しゃぶりをやめさせることで、出っ歯の改善が見込めます。
噛み合わせが深い
歯と歯を噛み合わせた際に下の歯が見えなくなるくらい上の歯が大きく被さってしまう「過蓋咬合(かがいこうごう)」。
放置すると歯並びの悪化や顎関節への悪影響が考えられます。また、下あごや下の歯への負担も増大するため、早めのアプローチが大切です。
一部の噛み合わせが逆
この状態は「交叉咬合(こうさこうごう)」「すれ違い咬合」ともいわれます。
きちんと噛むことができず、一部の歯への負担が大きくなり、歯の寿命を縮めてしまう原因になります。
【歯並び別】歯科矯正スタートにおすすめの年齢

ここからは歯並びの状態に合わせた、歯科矯正を始めるのにおすすめの年齢を紹介します。
なぜ歯並びによって歯科矯正を開始するのにおすすめの時期があるのかというと、上あごと下あごの発育スピードがそれぞれ異なるからです。
以下は上あご・下あごそれぞれの発育のピークの目安です。
- 上あごの成長のピーク(目安):10歳前後
- 下あごの成長のピーク(目安):男子は18歳ころまで・女子は15歳ごろまで
受け口:4歳から5歳ごろ
受け口の原因としては、
- 生まれつき下あごが上あごよりも大きい
- 下あごが上あごに比べて前に出過ぎている
- 下の前歯が前に突き出ている
といったものが考えられます。
上下のあごのバランスが原因で生じる受け口では、基本的に下あごが相対的・あるいは絶対的に大きくなっています。
そのため子どものころからの矯正では、上あごの成長を生かすための装置を装着することがあります。
上あごの成長のピークは10歳前後ですが、実は4歳から6歳ごろには上あごの成長の7割程度は完了するといわれています。
そのため子どもの受け口で悩んでいる場合は、上あごの成長期を逃さないよう、4歳から5歳ごろには歯科クリニックに相談し、あごの健やかな発育のためのサポートを受けられるようにしましょう。
出っ歯:8歳から10歳ごろ
出っ歯の原因としては
- 生まれつき上あごが下あごよりも大きい
- 上あごが下あごに比べて前に出過ぎている
- 上の前歯が前に突き出ている
といったものが考えられます。
出っ歯の矯正の場合は下あごの発育を促して治療を行うケースがあります。この場合は下あごの成長に合わせ、8歳から10歳ごろのスタートが理想的と言えるでしょう。
また、これは受け口も同様ですが、口まわりの悪習慣(指しゃぶり・口呼吸・爪を噛む など)が原因で前歯が突き出てしまっているケースもあります。
この場合は生え変わりの時期の悪習慣を改善するのが効果的。
たとえば「3歳を過ぎたのに1日6時間以上指しゃぶりをしている」といった気になる癖があれば、早めに歯科クリニックに相談したほうがいいでしょう。
ガタガタの歯:奥歯の噛み合わせ次第
歯がガタガタに並んでいる場合は、奥歯の噛み合わせ次第で、推奨される歯科矯正のスタート時期が異なります。
前歯がガタガタでも奥歯の噛み合わせに問題がない場合は、10歳から11歳ごろからの矯正スタートでも遅過ぎないことも。
一方奥歯の噛み合わせに問題がある場合は、少し早めの8歳から10歳ごろから矯正をスタートしたほうがいいでしょう。
なぜなら奥歯がうまく噛み合っていないと、以下のようなリスクがあるためです。
- 奥歯で食べ物を十分にすり潰すことができず消化器官に負担がかかる
- あごに過度の負担がかかり顎関節症を引き起こす
また、歯並びがガタガタですと、その分ブラッシングが行き届きにくく、むし歯リスクが高まります。
定期的なプロのクリーニングを受けるためにも、早めに歯科クリニックに相談してみましょう。
小児矯正にかかる料金・期間

子どもの歯科矯正を考えたとき、多くの親御さんが気になるのがコスト面ではないでしょうか。
また歯科矯正は長期間かかるイメージがあり、子どもへの精神的ストレスに不安を覚える親御さんもいらっしゃるでしょう。
そこでここでは、小児矯正にかかる料金・期間を紹介します。あくまでも目安にはなりますが、治療を受けるクリニックの比較検討の際の参考になると幸いです。
矯正時期 | 矯正費用(目安) | 治療期間(目安) |
|---|---|---|
【0期治療】 3歳〜5歳頃 | 3万〜10万円程度 | 1年〜2年程度 |
【1期治療】 6歳〜12歳頃 | 20万〜30万円程度 | 10ヶ月〜3年程度 |
【2期治療】 13歳以降 | 30万〜100万円程度 | 1年〜3年程度 |
保定期間も必要
歯科矯正は治療期間はもちろんですが、矯正終了後の保定期間も必要です。
なぜなら歯科矯正によって動いた歯は、何もしない状態だと元の位置に戻ろうとするためです。
上記の表に掲載している治療期間は、この保定期間を除いたものになっているので注意してくださいね。
保定期間は一般的に、矯正治療にかかった同じ期間必要とされています。
また保定装置(リテーナー)にかかる料金は1万円から6万円程度。さらに保定観察料も必要で、これは1回あたり5,000円程度が目安です。
ただし子どもの歯科矯正を行う歯科クリニックの中には、このような保定期間にかかる料金も含めたトータルフィーとしているところもあります。
この場合、保定にかかる追加料金は基本的に発生しません。
2期治療を割引してくれる場合も
子どもの歯科矯正の中でも、2期治療は基本的に大人の歯科矯正と行うことは同じです。
そのため子どもであっても、2期治療から歯科矯正をスタートする場合は、大人の歯科治療と同様のコストがかかる歯科クリニックもあります。
一方で0期治療や1期治療から歯科矯正を始めた場合、その際にかかった料金を2期治療から割引するような料金体系にしている歯科クリニックもあります。
また、歯科矯正にかかる料金をトータルフィーとしているクリニックの場合は、最初に歯科矯正にかかる料金を支払えば、その後の歯科矯正における追加料金は基本的に発生しません。
お子様が歯科矯正を受ける歯科クリニックを選ぶ際は、このような料金体系も比較しながら検討するといいでしょう。
子どもの歯並びの不安は早めに相談を

歯科矯正を何歳から始めるべきかは、子どもの歯やあごの状態によって異なります。
しかし「子どものあごの成長を生かした矯正をしたい」「固定式の矯正装置は子どものストレスになりそうだから避けたい」というのであれば、小児矯正を検討してみてはいかがでしょうか。
子どもの発育の段階に合わせた選択肢を提示してくれるクリニックなら、「今子どもの歯並びのためにできること」を教えてもらえます。
0期・1期治療の結果、2期治療が不要になれば、その分治療にかかる費用も抑えられます。
お子様の歯並びに不安がある場合は、早めに歯科クリニックに相談してみましょう。