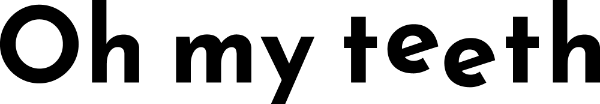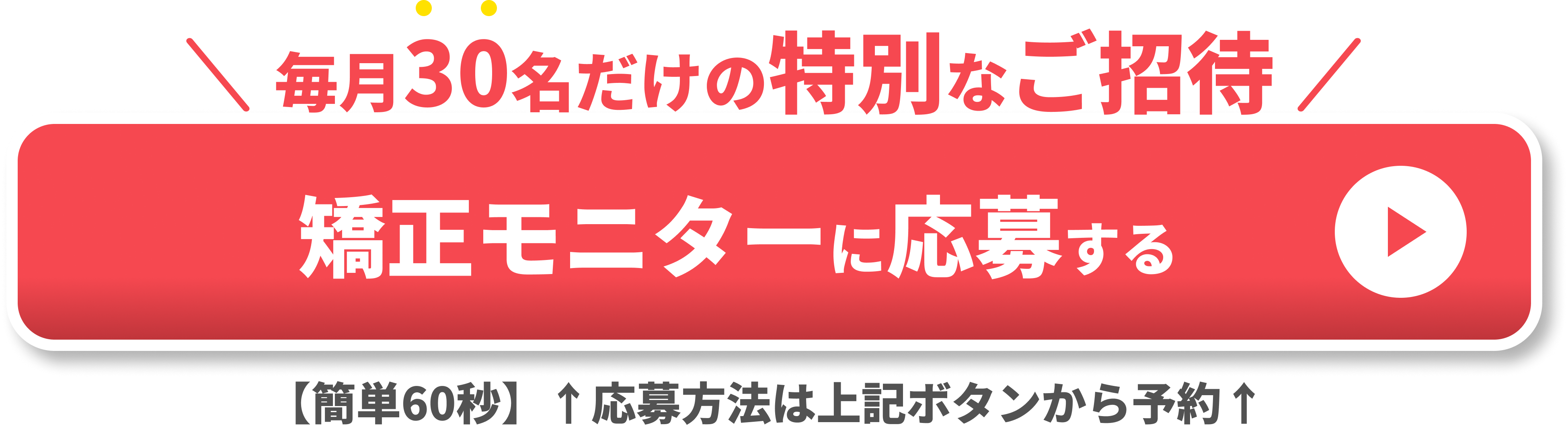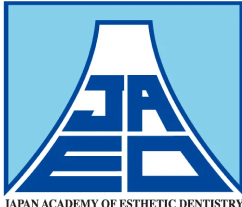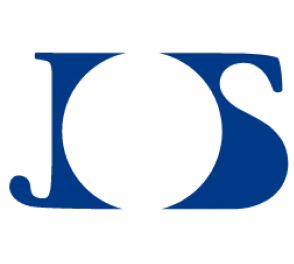コラム
最終更新日:2025年12月4日
開咬を自分で治すことは可能?原因と正しい対処法を解説

前歯が噛み合わず、口が閉じにくい「開咬(かいこう)」。
なんとか自分で治せないか…と考える人もいるかもしれませんが、残念ながら自己流での改善は難しく、かえって悪化するおそれもあります。
この記事では、開咬の原因や放置によるリスク、正しい治療法とあわせて、自分でできる予防や補助的なケアについても詳しく解説します。
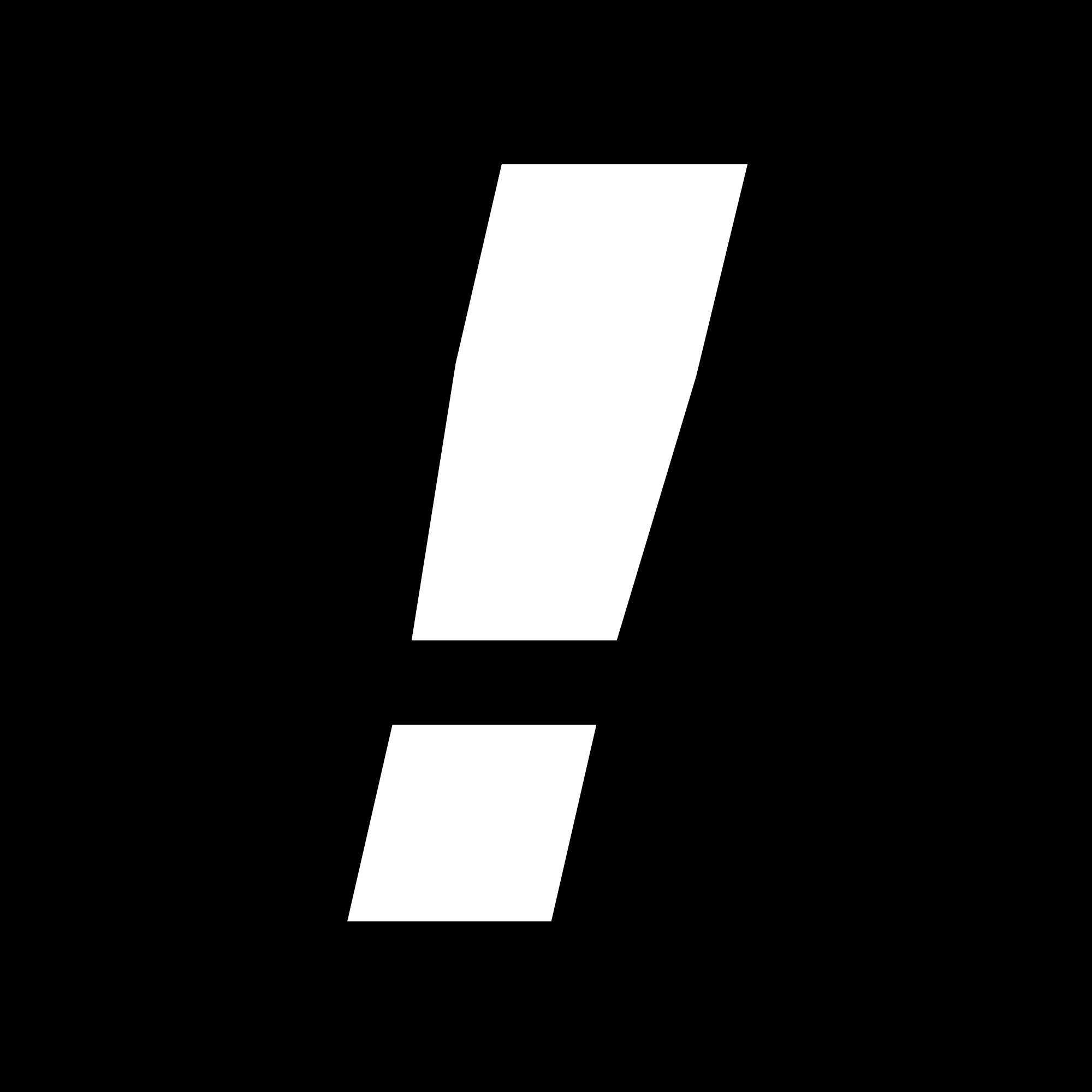
歯科矯正ブログ編集チーム
Oh my teeth
マウスピース矯正「Oh my teeth」ホームホワイトニング「Oh my teeth Whitening」を提供するOh my teethのコンテンツチームです。Oh my teeth導入クリニックのドクターと連携し、歯科矯正やホワイトニング、自社ブランドに関する確かな情報を発信しています。
そもそも開咬とは?

開咬(かいこう/別名:オープンバイト)とは、奥歯は噛み合っていても前歯が閉じず、上下にすき間ができてしまう噛み合わせのことです。
一般的に上下の前歯の噛み合わせにすき間がある状態を広く指すこともありますが、厳密には「上の歯が下の歯に垂直的に全く被っていない状態(オーバーバイトがマイナス値の状態※)」を指します。
たとえば、前歯で食べ物を噛み切るのが難しく、麺類やサンドイッチなどが食べづらいと感じる方は、開咬の可能性があります。前歯のすき間から空気が漏れることで、発音が不明瞭になることも多いです。
また、見た目が似ている歯並びに「出っ歯(上顎前突)」がありますが、これは別の不正咬合。
出っ歯は上の前歯が前方に突き出している状態で、上下の歯は一応接触しています。一方で、開咬は上下の前歯が接触せず、隙間ができているのが特徴です。
※オーバーバイトがマイナス値:垂直的な被盖距離(前歯同士の重なり具合)が0.0mm以下のもの
【結論】開咬を「自分で治す」のは不可能

結論から言うと、開咬を自分で治すことはほぼ不可能です。
舌の位置を意識したり、姿勢を正したりすることで「少し良くなった気がする」と感じることはあるかもしれませんが、根本的な改善にはつながりません。
ネット上では「トレーニングで治る」「マッサージで改善する」といった情報も見かけますが、医学的な根拠が乏しく、むしろ噛み合わせを悪化させる可能性もあります。
開咬は原因に応じた専門的な治療が必要です。まずは、自分の開咬がどのタイプかを正しく把握することが第一歩です。
開咬を治すには、原因や状態に合った治療法の選択がとても重要。
Oh my teeth では、歯科医師による無料診断を実施しており、治療の必要性や適した方法を丁寧にアドバイスします。
まずは開咬の原因を知ろう

開咬の改善には、まず原因を知ることが大切です。
原因によって対処法は大きく異なるため、「なぜ開咬になったのか」を正しく理解することが、適切な治療につなげる第一歩になります。
① 子どもの頃の癖(指しゃぶり・舌癖など)
小さい頃の癖が、大人になっても噛み合わせに影響を与えることがあります。
特に、指しゃぶりを長く続けていたり、舌で前歯を押す癖(舌癖)があると、前歯が押し出されて開咬の原因になる場合も。
乳歯の時期だからと軽視されがちですが、癖が残ったまま成長すると、永久歯の歯並びにも影響を及ぼします。
② 骨格的な問題(遺伝・顎の成長不全)
生まれつきの骨格や、顎の成長バランスが悪い場合にも開咬の原因の1つです。
たとえば、下あごの成長が過剰だったり、上あごの成長が不十分だったりすると、上下の歯がうまく噛み合わず、前歯にすき間ができる状態になります。
このような骨格性の開咬は、矯正治療だけでなく外科的な処置が必要になることが多いです。
③ 日常習慣(口呼吸・頬杖・寝姿勢など)
普段何気なく行っている習慣が、開咬を引き起こす原因になることも。
たとえば、いつも口を開けている口呼吸、片側ばかりに負担をかける頬杖、うつぶせ寝や横向き寝などの姿勢は、歯や顎に偏った力を与えてしまいます。
知らず知らずのうちに、噛み合わせがずれていくきっかけになるため注意が必要です。
開咬を放置するリスク

開咬は自然に治ることはほとんどなく、放置すると日常生活や健康面にさまざまな悪影響が出ることがあります。
ここでは開咬を放置しておくことで起こりうる主なリスクを見ていきましょう。
食事がしづらい
開咬の場合、前歯で食べ物をうまく噛み切ることができません。
たとえば、ハンバーガーやおにぎり、麺類などが食べづらく、かじりつく動作にストレスを感じる人も多いです。
その結果、奥歯に頼りすぎた食べ方になり、噛み合わせのバランスが悪化する悪循環に。
しっかり噛めないと消化不良の原因にもなり、胃腸への負担も増えてしまいます。
発音に悪影響がある
上下の前歯のすき間から空気が漏れることで、「サ行」「タ行」「ナ行」などの発音が不明瞭になりやすくなります。
「歯のすき間から息が抜けてしまって滑舌が悪く聞こえる」と悩む人も少なくありません。
とくに人前で話す機会が多い仕事をしている人にとっては、大きなコンプレックスになることもあります。
顎関節への負担
噛み合わせのバランスが悪いと、日常的に顎の筋肉や関節に無理な力がかかるようになります。
その結果、あごの痛み・疲れ・違和感、口の開けづらさなどの症状が現れ、「顎関節症」につながるケースも。
一度負担がかかった関節はなかなか元に戻らないため、できるだけ早めの対処が重要です。
虫歯や歯周病が起こりやすくなる
開咬では歯が均等に接触しないため、うまく歯磨きできない部分が出てきます。
歯の重なりやすき間に汚れがたまりやすくなり、気づかないうちに虫歯や歯周病が進行してしまうことも。
さらに、噛む力のバランスが悪くなると一部の歯に負担がかかり、歯がグラついたり、歯ぐきの炎症を引き起こす可能性もあります。
コンプレックスになり自信がなくなる
開咬の見た目が気になって、人前で笑うことや話すことに抵抗を感じる人もいます。
「口元が気になって写真が嫌い」「笑うとすき間が見えて恥ずかしい」など、本人にとっては深刻な悩みになることも。
外見のコンプレックスは気づかないうちに自己肯定感を下げ、人との関わりに消極的になるきっかけになってしまいます。
「開咬を自分で治す」=危険!正しい治療法は?

開咬を「なんとか自分で治したい」と思う気持ちはよくわかりますが、自己流の対応はとても危険です。
間違った方法で舌や顎に負担をかけてしまうと、症状が悪化したり、治療がより複雑になる可能性も。
開咬は、その原因や状態によって必要な治療法が異なります。
ここでは、主な治療法を見ていきましょう。
① マウスピース矯正(軽度なケース)
前歯の隙間が小さく、歯並びのズレが軽度な場合には、マウスピース矯正で対応できるケースもあります。
マウスピース矯正は透明で目立ちにくいマウスピースを使って、少しずつ前歯の位置を整える方法。
ただし、歯並びだけでなく「噛み合わせの改善」も目的とするため、必ず専門の歯科医師による診断が必要です。
あわせて読みたい

マウスピース矯正とは?歯の矯正に使えるマウスピースの特徴・費用・注意点まとめ
② ワイヤー矯正(中〜重度)
開咬が中〜重度の場合や、奥歯にもズレがある場合には、ワイヤー矯正による本格的な治療が必要になります。
ワイヤー矯正は歯をを立体的に動かすことができるため、前後・上下・左右といった細かな位置調整が可能です。
そのため、噛み合わせをしっかり整える必要がある症例にも対応しやすいのが特徴があります。
あわせて読みたい

ワイヤー矯正とは?ワイヤーの種類や仕組み、特徴を徹底解説
③ 外科的治療(骨格性開咬)
顎の骨格自体に原因がある「骨格性開咬」の場合、矯正治療だけでは改善が難しく、外科的な手術が必要になることもあります。
顎の位置を外科手術で調整したうえで、矯正治療を組み合わせることで、しっかり噛み合う状態を目指します。
治療期間は長くなりますが、根本から噛み合わせを整えられるのがメリットです。
自分でできる予防・補助ケアは?

開咬は自分で治すことはできませんが、悪化を防いだり、治療の効果を高めるために、日常生活の中でできることもあります。
以下のようなポイントを意識することで、開咬の進行予防や治療効果のサポートにつながります。
①舌の正しい位置を意識する
舌先は上あごの前歯のすぐ後ろ(スポット)につけるのが正しい位置。
飲み込むときや話すとき、この位置を意識することで、舌癖の改善につながります。
②猫背やうつむき姿勢を避ける
前かがみの姿勢は顎の位置をずらし、口呼吸や舌癖を引き起こす原因に。
スマホやPC作業中は、背筋を伸ばし鼻呼吸を意識しましょう。
③頬杖・うつぶせ寝などの癖を見直す
一方向への力が続くと噛み合わせがずれやすくなります。
無意識のクセがないか、日常生活をチェックしてみてください。
④口呼吸をやめて鼻呼吸を意識する
常に口が開いていると、舌が下がった位置になりがちです。
口を軽く閉じ、鼻で呼吸する習慣をつけることも、舌の位置安定につながります。
ただし、セルフケアはあくまで専門的な治療と併用して行う補助的なものです。
まずは専門医による診断を受けたうえで、適切な治療とあわせて実践していきましょう。
開咬を自分で治すのは危険!まずは専門医に相談を

開咬は、原因や症状の度合いによって必要な治療法がまったく異なるため、自己判断で対応するのはとても危険です。
ネット上の情報を参考にしたり、自分なりのマッサージやトレーニングを試しても、かえって噛み合わせが悪化してしまう可能性があります。
開咬を根本から改善するには、歯科医師による正確な診断が必要不可欠です。
特に「見た目が気になる」「食べづらい」「発音がしにくい」など、日常生活で違和感がある場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。
「自分の歯並びも開咬なのか気になる」「まずは専門医に相談だけでもしてみたい」という方には、マウスピース矯正 Oh my teeth の無料診断がぴったり。
Oh my teeth では、歯科医師による口腔内チェック・レントゲン撮影・スキャンを含む本格的な診断を無料で実施しています。まずはお気軽にあなたの歯並びをチェックしてみませんか?