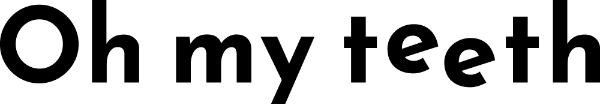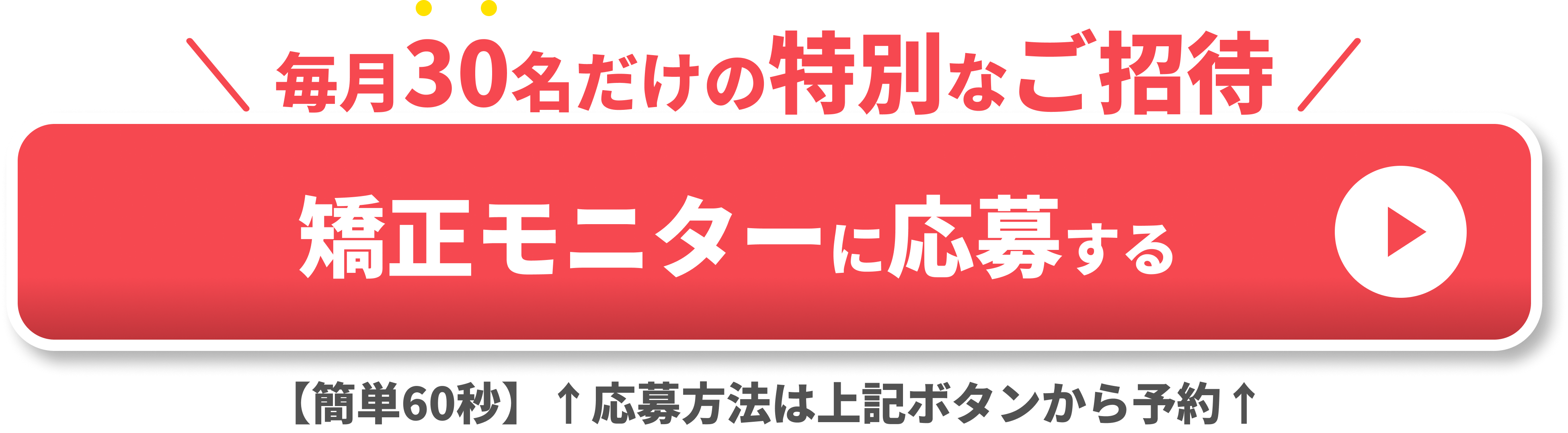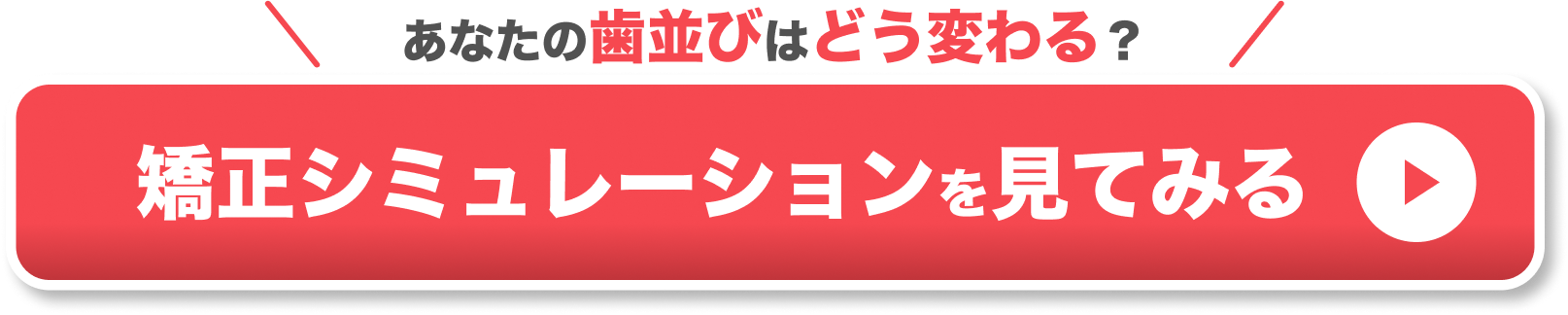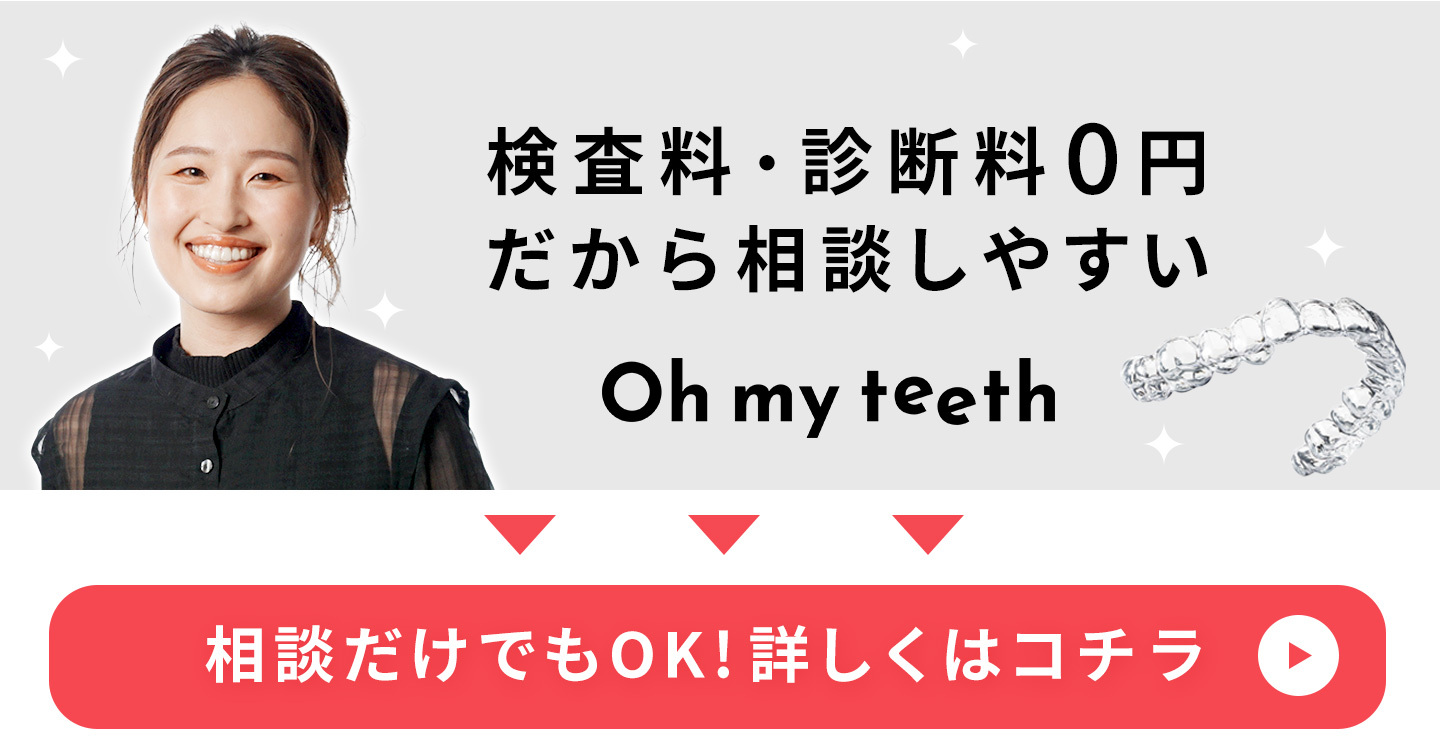オーラルケア
最終更新日:2025年6月5日
歯石ができやすい人の特徴8選|あなたは当てはまる?原因と今日からできる予防法

毎日歯磨きをしているのに、いつも歯科クリニックで歯石(しせき)ができていると指摘されてはいませんか。
そのような人は体質的に歯石ができやすいか、無意識に歯石ができやすい生活を送っている可能性が高いです。
この記事では、「歯石ができやすい人に見られる8つの特徴」について解説します。
歯石ができる根本の理由や、歯石をつきにくくする対策も紹介しているので、歯石でお悩みの方はぜひ参考にしてください。
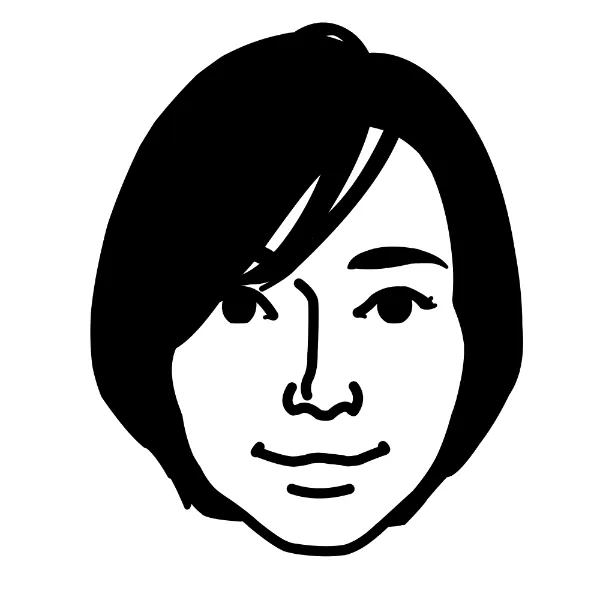
歯科矯正ブログ編集チーム
木村真由美
Oh my teethでのマウスピース矯正を経て、2021年6月に株式会社Oh my teethにジョイン。マウスピース矯正経験者としてOh my teethのオウンドメディア「歯科矯正ブログ」にて記事を更新中。ミッションは「歯並びに悩むすべての方に歯科矯正の確かな情報をお届けすること」。
歯石ができやすい理由とは

歯石(しせき)とは、歯に付着した歯垢(しこう。プラークとも言う)が唾液に含まれるミネラルと結合し、石のように硬くなったものです。
個人差がありますが、歯垢は一般的に約48時間で固まりはじめ、その後14日程度で歯石になるとされています。
歯石は歯垢と唾液によって形成されるため、唾液の性質(体質)の影響も受けます。
歯石ができやすい人の特徴
- 唾液の量が多い
- 唾液がサラサラしている
- 唾液がアルカリ性に近い
唾液がアルカリ性に近い人は歯石ができやすい一方、酸性になっている口内を中和させるため、虫歯ができにくい傾向にあります。
しかし、ずっと虫歯ができていないからといって、歯科クリニックでの定期健診を怠り、その結果、知らず知らずのうちに歯石が溜まっていたというケースは少なくありません。
歯石には軽石のように小さな穴がたくさん空いており、口内細菌にとっては恰好の住処となります。
放置していると歯周病や虫歯のリスクが高くなるため、こまめに歯科クリニックでメンテナンスをすることが大切です。
歯石ができやすい人に多い8つの特徴

歯石は体質だけでなく、生活習慣によってもできやすくなります。ここでは、歯石ができやすい人に多くみられる8つの特徴を一つひとつ見ていきましょう。
歯磨きが十分にできていない
歯磨きが不十分だと歯垢が溜まり、歯石ができやすくなります。
もし以下のいずれかに該当する場合は、歯磨きをしているつもりでも磨き残しがあるかもしれません。
- 歯磨きの回数が1日1回以下
- 歯磨きの時間が短い
- 口に合わない歯ブラシを使っている
- 古い歯ブラシを使っている
また、毎日のケアを歯ブラシのみで済ませている人は、歯間ブラシやフロスを使っている人に比べて歯石ができる可能性が高いです。
なぜなら、歯ブラシだけでは6割程度の汚れしか落とせないからです。とくに歯間や歯茎は歯ブラシが届きにくいため磨き残しが発生しやすく、歯垢が溜まって歯石ができやすくなります。
口呼吸が癖になっている
口呼吸が癖になっている場合、唾液の自浄作用が働きにくく、歯石ができやすいです。
唾液の自浄作用とは、歯に付着した食べカスなどの汚れを洗い流し、歯垢の発生を抑える働きのこと。
前述の通り、唾液の分泌量が多い人は歯石ができやすい傾向がありますが、反対に唾液の量が少なく口が乾いている場合も、歯垢が溜まりがちになり、そのぶん歯石ができやすくなります。
口の乾きは習慣的な口呼吸だけでなく、普段から水分の摂取量が少ない場合や、飲酒・喫煙の回数が多い場合も起こりやすいので注意しましょう。
歯並びが悪い
歯がデコボコに並んでいたり、歯と歯が重なっていたりすると、歯磨きをしてもブラシがうまく届かず歯石ができやすくなります。
なかでも、上の奥歯や下の前歯の裏側はとくに歯石ができやすいので、歯磨きの際には重点的に磨くようにしましょう。
なお、歯並びは矯正で改善が期待できるので、「歯のがたつきが気になる」という方は歯科矯正を検討してみましょう。
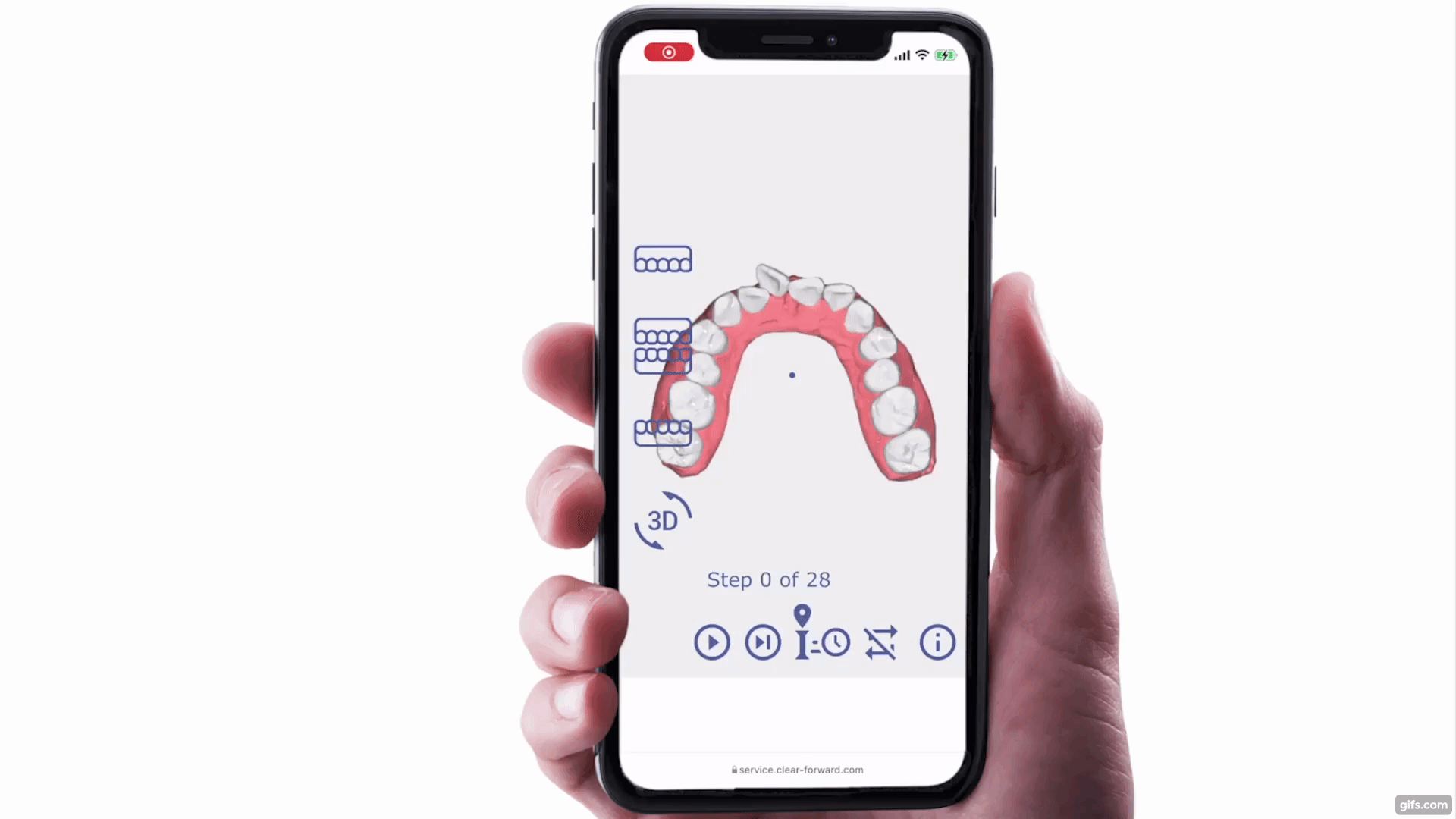
甘いものをよく食べる
甘い食べ物には、口内細菌の好物である糖分が多く含まれています。
そのため、甘いものを食べてばかりいると、歯磨きで落とし切れなかった糖分によって口内細菌が繁殖し、歯垢や歯石がつきやすくなります。
やわらかいものをよく食べる
やわらかい食べ物は歯と歯の間や歯茎との境目など、歯ブラシが届きにくい部分に食べかすが詰まりやすいです。
そのため、普段からやわらかいものばかりを食べていると、磨き残しによって歯垢が溜まり、歯石ができやすくなります。
また、噛む回数が減るため、唾液が分泌されにくく、その結果自浄作用が低下して歯垢や歯石ができやすくなります。
アルカリ性の食品をよく食べる
前述の通り、唾液がアルカリ性に近いと、歯石ができやすい傾向にあります。
唾液のpH(ペーハー)は平均6.8〜7.0とされており、中性または中性に近い弱酸性であることが多いです。
しかし、アルカリ性食品ばかりを食べている方は、唾液のpHがアルカリ性に傾きやすくなります。
アルカリ性の食品の一例としては、以下のような食べ物が挙げられます。
- 野菜
- 果物
- 海藻
- きのこ
- 大豆
- 梅干し
- お酒 など
なお、これらの食べ物を1度食べたからといって、唾液がすぐにアルカリ性に傾くわけではありません。
唾液がアルカリ性に傾きやすいのは、あくまでも普段の食生活がアルカリ性の食品に偏っている場合です。
たばこを吸っている
たばこを吸っている方は、たばこを吸っていない人に比べて歯石ができやすいです。なぜなら、たばこに含まれるタール(ヤニ)が歯石ができやすい環境をつくるためです。
タールは時間が経つと唾液に含まれるペリクルという成分と結び付いて、歯に定着する性質があります。歯にタールがこびりついた場合、歯ブラシだけでは汚れを除去できません。
また、タールは粘着性が高く、歯垢が付着しやすいため、歯に定着したタールに歯垢が付着すると、歯垢そのものが落ちにくくなり歯石が形成されます。
歯石ができやすい人に知っておいてほしい予防法の対策

歯石は、歯垢が唾液に含まれるミネラルと結びついて固まったものなので、歯石を予防するには原因となる歯垢を除去することが大切です。
ここでは歯石ができやすい人に知っておいてほしい、4つの対策を紹介します。
歯磨きを徹底する
自身でできる歯石予防として身近にできるのが、歯磨きを徹底することです。毎食後に歯磨きをすることで、歯垢を除去できるため歯石ができにくい口内環境をつくれます。
ただし、歯磨きだけで落とせる汚れは全体の6割程度です。歯と歯の間や歯茎との境目などに溜まった歯垢は、歯間ブラシやデンタルフロスを使用して取り除きましょう。
また、リステリンやピュオーラなどのマウスウォッシュは、歯垢の沈着予防に効果的です(歯石除去はできないのでご注意を)。歯磨き後に使用することで、さらに歯石ができにくい口内環境になります。
歯科クリニックでクリーニングを受ける
歯間ブラシやデンタルフロスを使っても、セルフケアだけでは歯垢を完全に取り除けません。
そのため、セルフケアで除去しきれない歯垢は、歯科クリニックのクリーニングで取り除いてもらうのがおすすめです。
歯科クリニックにより歯のクリーニングの内容が異なりますが、一般的には専用器具と薬剤を使用し、歯に付着した歯垢・歯石・着色を取り除きます。
クリーニング後は歯の表面がツルツルになり、歯垢が付着しにくい状態になるため、定期的にクリーニングを受けることで歯石ができにくくなります。
生活習慣を見直す
歯石ができやすい人は、生活習慣に原因が隠れている場合もあります。
とくに食生活は歯垢や歯石との関わりが深いため、甘いものややわらかいものを食べることが多い方は食生活を見直すと改善が見込めるかもしれません。
また、「口呼吸が習慣になっている」「喫煙や飲酒の回数が多い」などの場合は、唾液の分泌量が減りやすく、歯垢が溜まって歯石ができやすくなります。
歯石ができやすい方は、日頃のケアに加えて、ぜひ生活習慣も見直してみましょう。
歯科矯正を検討する
歯並びの悪さが原因で歯垢が溜まりやすい人は、歯科矯正を検討するのも一つの手です。
歯がデコボコに並んでいる場合や、歯と歯が重なっている場合は、歯並びを整えることで歯石ができにくくなる可能性が高いです。
また、矯正後は歯垢が除去しやすくなるため、虫歯や歯周病の予防にも効果が期待できます。
歯石を自分でとるのは危険

結論から言うと、歯石は「スケーラー」と呼ばれる専用器具を使えば自身で除去できます。しかし、歯石を自分でとるのは危険をともなうので注意が必要です。
スケーラーは先端が針金のように鋭く尖っているため、使用方法を間違えると歯茎を傷つけてしまう恐れがあります。
また、歯石がつきやすい上の奥歯や下の前歯の裏側は、自分で目視するのが難しいため、セルフで除去しようとしてもとり残す可能性も高いです。
万が一のトラブルを防ぐためにも、歯石の除去は歯科クリニックにお願いしましょう。
歯石ができやすい人は対策を徹底することが大切
歯石は、歯の表面にできた歯垢が時間の経過とともに固まってできます。そのため、歯石ができやすい人は、歯石ができる前に歯垢をしっかり除去することが大切です。
歯垢を残さないためにも、歯磨きなどセルフケアの徹底と、歯科クリニックでの定期的なクリーニングを心がけましょう。
また、生活習慣や歯並びが原因で歯石ができやすい人は、原因を突き止め対策をとることで、より歯石ができにくい口内環境へと改善できます。
なお、マウスピース矯正 Oh my teethでは、精密検査・診断が無料で受けられます。
「歯並びが悪く、毎日の磨き残しが気になる」
「歯石ができやすいのは歯並びが原因かも」
「歯石ができやすいのは歯並びが原因かも」
という方は、ぜひお気軽に無料診断へお越しください。歯石ができにくい歯並びへ導くサポートをいたします。