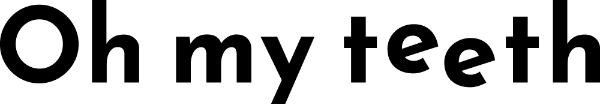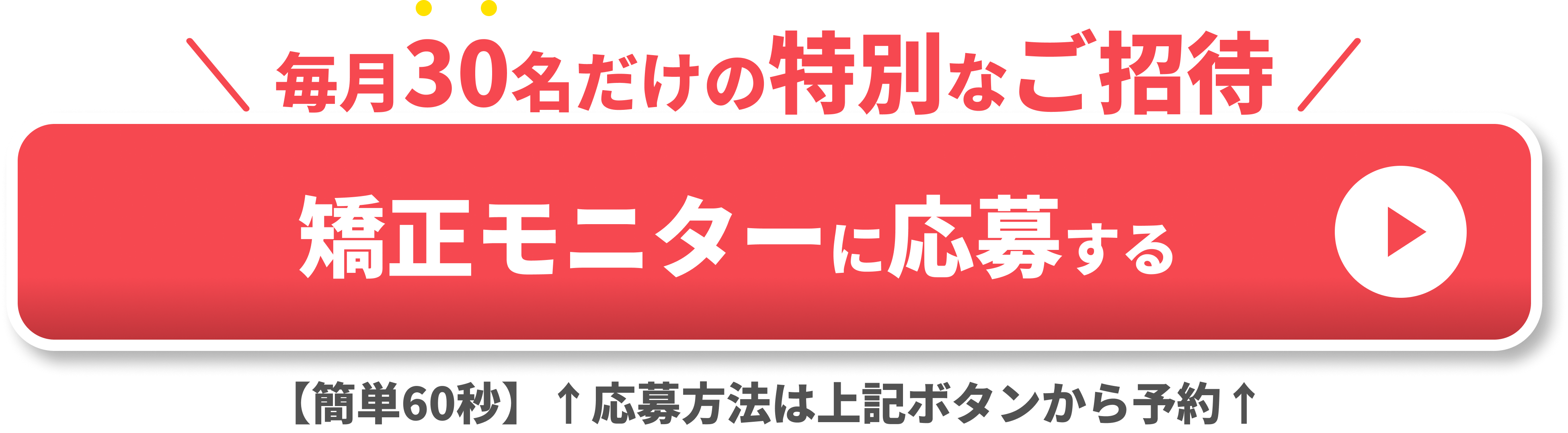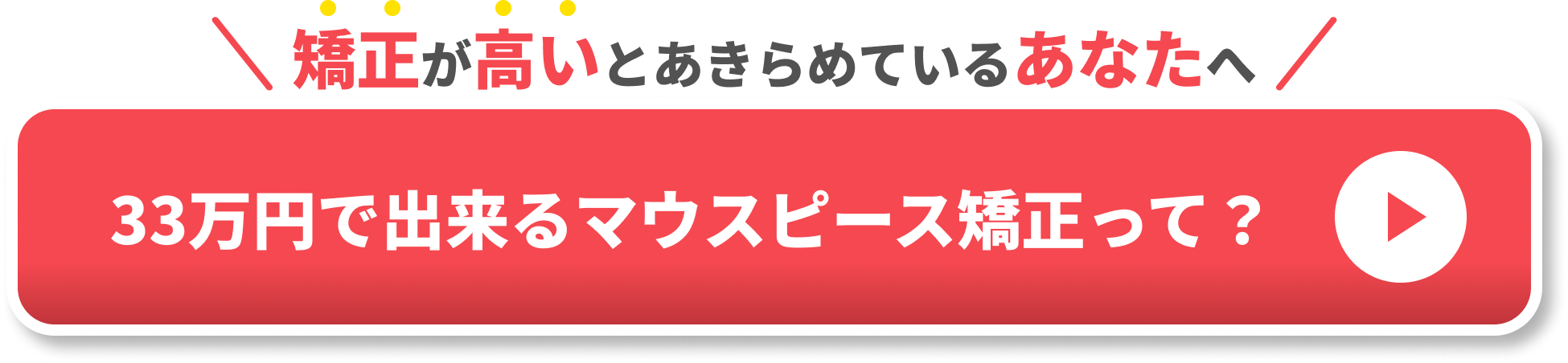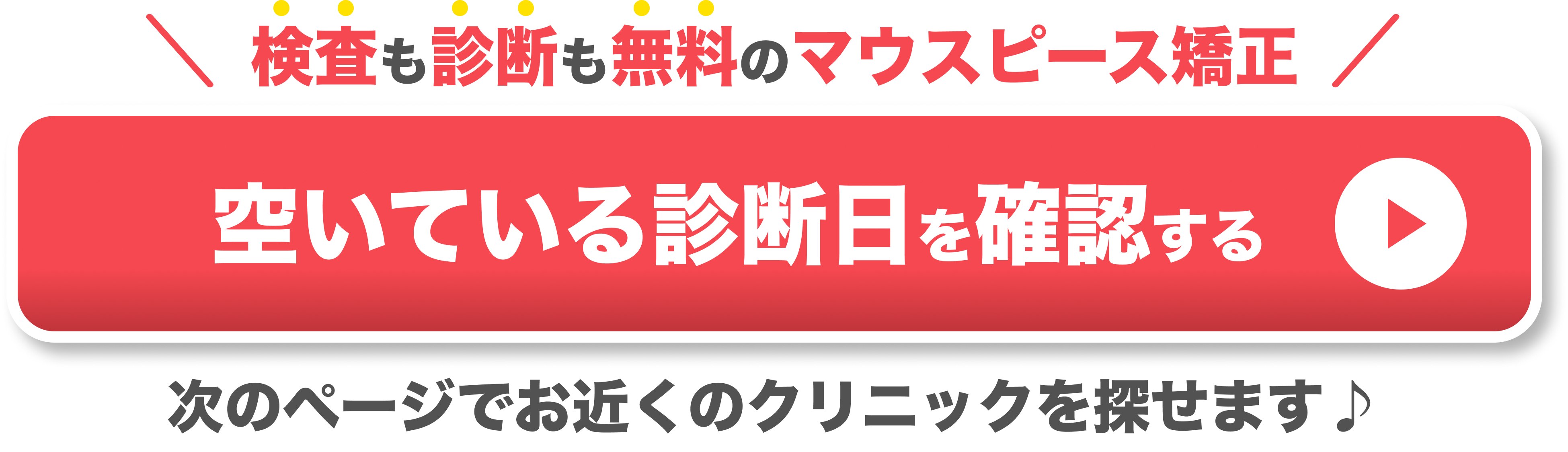歯科矯正
最終更新日:2025年6月26日
頭痛が続くのは噛み合わせのせい?見逃されがちな原因と治療法を解説
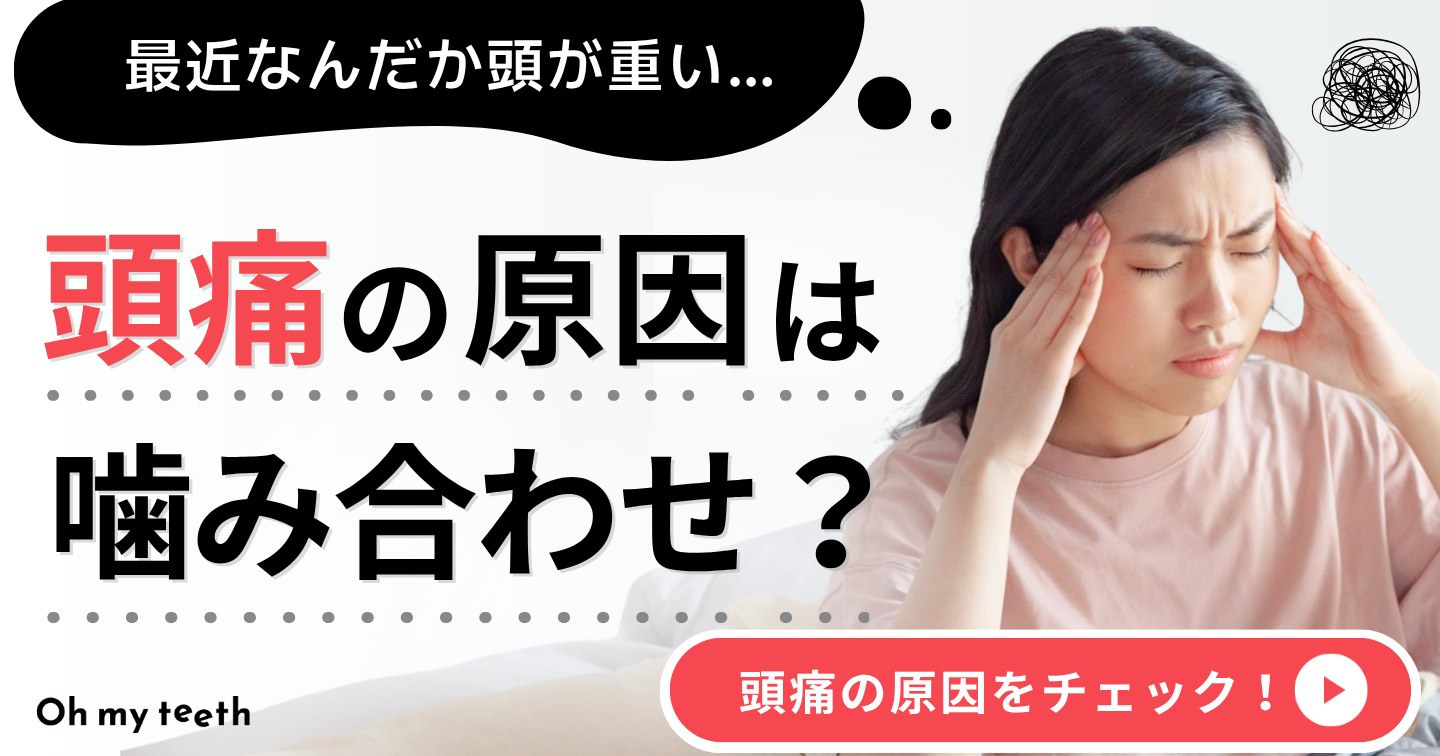
「最近、なんだか頭が重い」「顎の痛みとともに頭痛が続く」などの不調に悩まされていませんか。
もしかすると、その原因は噛み合わせの乱れにあるかもしれません。
噛み合わせが悪いと、顔まわりの筋肉や顎の関節に負担がかかり、頭痛や肩こり、めまいなどを引き起こすことがあります。
この記事では、噛み合わせと頭痛の関係や、自分でできるチェック方法、治療の選択肢についてわかりやすく解説します。
「病院では異常がないと言われたけれど、不調が続いている」という方は、ぜひ参考にしてください。

目次
- 【結論】噛み合わせが悪いと頭痛を引き起こす
- 悪い嚙み合わせが頭痛を引き起こす原因は?
- ①顔周りに筋肉の緊張と血流の悪化を引き起こすから
- ②噛み合わせが姿勢のバランスを崩すから
- ③自律神経が乱れるから
- こんな噛み合わせは要注意?セルフチェックしてみよう
- 噛み合わせが悪くなる原因は?
- 先天的な歯並び・顎の骨格の問題
- 姿勢の悪さや生活習慣の癖(歯ぎしりや食いしばりなど)
- 親知らずや欠損歯の放置
- 顎関節症の発症
- 噛み合わせの悪さによる頭痛を根本的に改善する方法は?
- マウスピース矯正
- ワイヤー矯正
- 親知らずの抜歯や抜けた歯の治療
- 生活習慣や悪癖の改善
- 【頭痛以外】噛み合わせが悪いと起こる体の不調は?
- 噛み合わせの悪さに伴う頭痛は放置しないで!まずは歯科医院で相談を
- Oh my teethの無料診断で頭痛の原因を解消できるか確認してみよう
【結論】噛み合わせが悪いと頭痛を引き起こす
噛み合わせの悪さが、慢性的な頭痛の原因になることがあります。
その理由は、歯やあごのバランスが乱れることで、顔まわりや首、肩の筋肉が緊張しやすくなり、血流が滞るなどして痛みを引き起こすためです。
また、噛み合わせの不調は、姿勢の崩れや自律神経の乱れにもつながり、頭痛だけでなくめまいや肩こりなど、さまざまな体調不良を誘発するケースもあります。
このように、原因不明の頭痛が長引いている場合は、「噛み合わせ」に目を向けることが、根本改善への第一歩になるかもしれません。
悪い嚙み合わせが頭痛を引き起こす原因は?

噛み合わせが乱れると、顔まわりの筋肉や神経に過剰な負担がかかり、頭痛を引き起こすことがあります。
これは、噛み合わせの不調が身体の広範囲に影響するためで、特に以下の3つのメカニズムが大きく関係しています。
①顔周りに筋肉の緊張と血流の悪化を引き起こすから
噛み合わせが悪いと、顔まわりの筋肉がこり固まり、血流が悪くなることで頭が痛くなることがあります。
歯がうまくかみ合っていないと、顎の周りの筋肉に余計な力が入り、これが毎日続くと顔やこめかみの筋肉がガチガチにこって血流が悪くなってしまいます。
血の流れが悪くなると、頭のまわりに酸素や栄養が届きにくくなり、ズキズキ・重だるいといった頭痛が起きやすくなるのです。
②噛み合わせが姿勢のバランスを崩すから
噛み合わせの乱れは、姿勢のバランスを崩し、首や肩に負担をかけることで頭痛を引き起こします。
本来、歯の噛み合わせは頭と体をまっすぐに支える土台の役割を担っています。
しかし、噛み合わせが左右どちらかに偏っていたり、上下の歯が正しく噛み合っていなかったりすると、顎の位置がズレて体のバランスが崩れます。
その結果、頭を支える首や肩に無理な力がかかり、筋肉の緊張に伴う頭痛が発生するのです。
③自律神経が乱れるから
噛み合わせの乱れは、自律神経のバランスを崩し、頭痛の原因になることがあります。
自律神経とは、呼吸・血圧・体温・睡眠などを自動的に調整してくれる神経で、「交感神経(活動モード)」と「副交感神経(リラックスモード)」がバランスよく働くことで、心身の状態を整えています。
しかし、噛み合わせが悪いと、顎の筋肉に力が入りやすくなり、体がストレスを受けていると判断して交感神経が過剰に働くようになります。
その結果、自律神経のバランスが乱れ、血流の悪化や睡眠の質の低下を招き、慢性的な頭痛につながる場合があるのです。
こんな噛み合わせは要注意?セルフチェックしてみよう

「頭痛が噛み合わせからくる」と言われても、自分の噛み合わせが正しいのかどうか、ピンとこない方も多いのではないでしょうか。
まずは、ご自身の噛み合わせが次のポイントを満たしているか、鏡の前でチェックしてみましょう。
正しい噛み合わせの7つのポイント
- 上下の前歯の間にすき間がない(あっても5mm以下)
- 下の前歯が上の前歯よりも内側に収まっている
- 歯列全体が左右対称で、なめらかなU字型をしている
- 上の前歯2本が大きく、下の前歯2本が小さい
- 上下の前歯の真ん中が揃っている
- 奥歯同士がきちんと噛み合っている
- 無理なく口を閉じることができる
これらのうち当てはまらない項目がある場合、正しい噛み合わせではない可能性があります。
さらに、普段の生活の中で以下のような症状がある方も、噛み合わせに問題があるかもしれません。
日常生活での「噛み合わせ異常」セルフチェック
- 割りばしを横にくわえて軽く噛んだとき、割りばしが水平にならず、左右どちらかに傾く
- 噛んでいるとあごに違和感や痛みを感じる
- 食事中、いつも決まった片側だけで噛んでしまう
- 歯磨きのとき、片側の奥歯ばかりに食べカスが溜まりやすい
- 片方のあごばかり疲れる、だるくなる
- あごの開け閉めで「カクカク」や「ミシミシ」といった音がする
- 朝起きたとき、あごがこわばっている・開けづらい
- 大きく口を開けたときに痛みがある
- 長時間話すとあごが疲れる
噛み合わせが悪くなる原因は?

「噛み合わせが悪いのは生まれつきだから仕方ない」と思っている方も少なくありませんが、実はそうとは限りません。
噛み合わせの乱れは、遺伝だけでなく、日々の生活習慣や体の使い方によっても起こります。
ここからは、噛み合わせが悪くなる主な4つの原因について見ていきましょう。
先天的な歯並び・顎の骨格の問題
噛み合わせが乱れる原因として、もともとの歯並びや顎の骨格の形に問題があるケースは多いです。
人の歯や顎の形は個人差が大きく、親からの遺伝で歯がガタガタだったり、成長の過程で顎が前に出たりすることがあります。
その結果、上下の歯がうまくかみ合わず、次のような不正咬合(ふせいこうごう)と呼ばれる悪い噛み合わせにつながってしまうのです。
代表的な不正咬合の6タイプ
- 上顎前突(出っ歯):上の前歯や上あごが前に突き出している状態
- 下顎前突(受け口):下あごが前に出ていて、下の前歯が上の前歯よりも前にある状態
- 開咬(オープンバイト):奥歯はかみ合っているのに、前歯にすき間があって閉じられない状態
- 過蓋咬合(ディープバイト):かみ合わせが深く、上の前歯が下の前歯を覆い隠してしまう状態
- 空隙歯列(すきっ歯):歯と歯の間にすき間が空いている状態
- 叢生(乱ぐい歯):歯が重なり合ってデコボコに生えている状態
姿勢の悪さや生活習慣の癖(歯ぎしりや食いしばりなど)
普段の姿勢の悪さや生活習慣の癖も、噛み合わせの乱れを引き起こす大きな要因のひとつです。
本来、顎は体全体のバランスの中で正しい位置に保たれていますが、姿勢が崩れることで噛み合わせのずれにつながってしまうのです。
また、日常の何気ない習慣にも注意が必要です。
とくに歯ぎしりや食いしばりは、睡眠中など自分では気づかないうちに強い力がかかっており、歯のすり減りや噛み合わせの悪さの原因にもなります。
あわせて読みたい

歯ぎしり・食いしばりがひどくてもマウスピース矯正はできる?対策や注意点を解説
親知らずや欠損歯の放置
親知らずや歯の欠損を放置することで、噛み合わせが乱れるケースも少なくありません。
たとえば、親知らずが斜めや横向きに生えてしまうと、隣の歯を圧迫したり、歯列全体を押し出すように力が加わったりします。
その結果、周囲の歯が少しずつズレてしまい、噛み合わせに影響が出てくるのです。
また、虫歯や事故などで歯を失い、そのまま放置していると、空いたスペースに隣の歯が倒れ込んできたり、噛み合っていた反対側の歯が伸びてきたりすることがあります。
このようにして上下左右のバランスが崩れると、本来の噛み合わせが保てなくなっていきます。
あわせて読みたい

親知らずは歯並びを悪くする?矯正するなら抜いた方がいいの?
顎関節症の発症
顎関節症(がくかんせつしょう)も、噛み合わせが乱れる大きな原因のひとつです。
顎関節症とは、口を開け閉めする関節(顎関節)やその周囲の筋肉に不調が生じる疾患のことで、「顎がカクカク鳴る」「口が大きく開かない」「顎が痛い」といった症状が代表的です。
この疾患の原因はさまざまですが、関節や筋肉にかかる力のバランスが崩れることによって、噛み合わせが変化してしまうことも少なくありません。
噛み合わせの悪さによる頭痛を根本的に改善する方法は?
噛み合わせの乱れが原因で起こる頭痛は、市販薬などの対症療法だけでは根本的な解決になりません。
根本的に症状を改善するためには、噛み合わせ自体にアプローチすることが重要です。
ここからは、噛み合わせの改善に役立つ代表的な治療方法を4つご紹介します。
マウスピース矯正

軽度〜中等度の噛み合わせの乱れには、マウスピース矯正が有効な治療方法です。
透明なマウスピースを使って歯を少しずつ動かし、理想的な位置に整えていく矯正方法で、見た目が目立ちにくく、取り外しもできることから、忙しい方や矯正に抵抗がある方にも人気です。
とくに、前歯のガタつきや軽度の開咬・すきっ歯など、比較的シンプルな症例に適しており、歯並びだけでなく噛み合わせのバランスを整えることもできます。
ただし、装着時間を自身で管理する必要があるので、その点は注意が必要です。
「噛み合わせが少し気になる」「矯正はしたいけど目立つのは嫌」という方に、マウスピース矯正はおすすめの選択肢といえるでしょう。
ワイヤー矯正

噛み合わせのズレが大きい場合や、骨格に原因がある中等度〜重度の症例には、ワイヤー矯正が適しています。
ワイヤー矯正は、歯の表面に装置(ブラケット)をつけ、そこにワイヤーを通して歯を少しずつ動かしていく矯正方法です。
細かい調整がしやすく、奥歯を含めた全体的な歯列や噛み合わせの改善に効果的です。
見た目が気になるという声もありますが、近年では目立ちにくいセラミックブラケットや裏側矯正(リンガル矯正)なども選べるようになり、審美面にも配慮できるようになっています。
マウスピース矯正では対応しきれない複雑なケースには、ワイヤー矯正が第一選択となることが多いでしょう。
親知らずの抜歯や抜けた歯の治療
噛み合わせを整えるためには、親知らずや欠損した歯の適切な処置も欠かせません。
たとえば、斜めや横向きに生えてきた親知らずは、周りの歯を押し出したり、歯並びを乱す原因になることがあります。
このような場合、不要な親知らずは抜歯によって歯列への影響を最小限に抑えることが可能です。
また、虫歯や外傷などで歯を失い、そのまま放置していると、空いたスペースに隣の歯が傾いたり、反対側の歯が伸びたりして、噛み合わせのバランスが崩れます。
こうした欠損した歯も適切な処置によって補うことで、噛み合わせの安定につながります。
生活習慣や悪癖の改善
噛み合わせの乱れは、毎日の生活の中にある無意識の癖や習慣からも引き起こされるため、それらを改善することでも改善が見込めます。
たとえば、次のような習慣は、歯や顎に余計な負担をかけ、噛み合わせのバランスを崩す原因になります。
- 片側ばかりで食べ物を噛む
- 就寝中の歯ぎしり・食いしばり
- 頬杖をつく
- うつ伏せや横向きで寝るクセ
- 長時間スマホやPCを見続けて前かがみになる姿勢
これらのクセが長く続くと、筋肉の緊張や顎のズレにつながり、結果的に頭痛や肩こりなどの不調につながります。
そして、矯正や歯の治療を行う際も、こうした生活習慣が改善されていないと、せっかく整えた噛み合わせが再び乱れることもあるのです。
噛み合わせの治療をより効果的にするためには、日常生活を見直し、身体に負担をかけない姿勢や習慣を意識することも重要です。
【頭痛以外】噛み合わせが悪いと起こる体の不調は?

ここまで、噛み合わせの悪さに伴う頭痛について解説してきましたが、噛み合わせの乱れが引き起こすのは、頭痛だけではありません。
歯や顎の問題は、全身のバランスや神経に影響を与えることがあり、「咬合関連症(こうごうかんれんしょう)」と呼ばれるさまざまな不調の原因になることがあります。
- 顎関節の痛みや「カクカク」といった音が鳴る
- 口が開かない・開けるときに痛みがある
- 首こりや肩こり
- 耳鳴り・耳の詰まり感・難聴
- めまいや立ちくらみ
- 腰痛
- 手足のしびれ・膝の痛み など
これらの症状は、単独で見ると噛み合わせとの関係がわかりにくいため、原因が特定されずに長年悩んでいる方も少なくありません。
もちろん、すべての不調が噛み合わせによるものとは限りませんが、噛み合わせの乱れとあわせて気になる症状がある方は、歯科医院で噛み合わせのチェックを受けてみるのをおすすめします。
あわせて読みたい
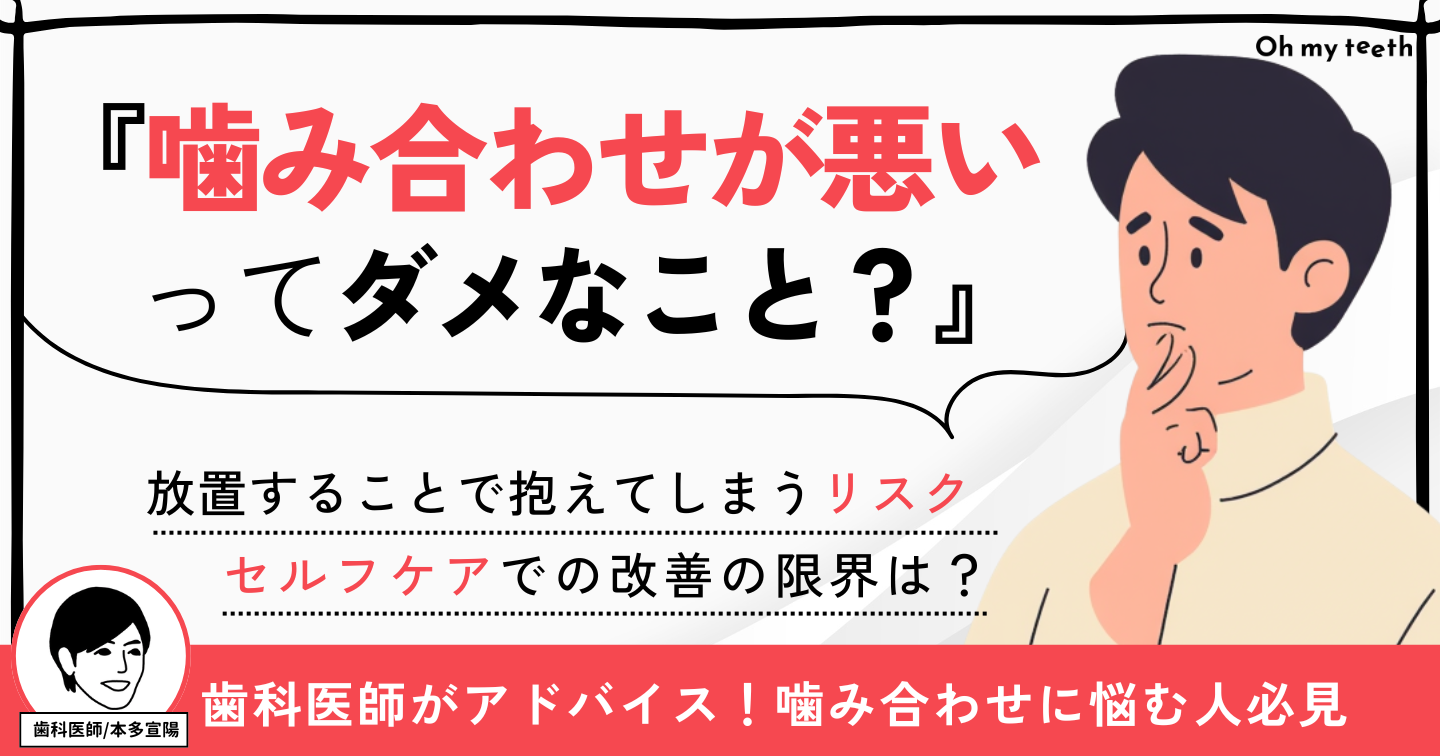
噛み合わせが悪いってダメなこと?放置するリスクと対処法を紹介
噛み合わせの悪さに伴う頭痛は放置しないで!まずは歯科医院で相談を
原因不明の頭痛が続いている場合、噛み合わせの乱れが関係していることがあります。
歯科医院では、噛み合わせや顎の動き、歯列のバランスを確認し、必要に応じて治療を提案します。
病院で異常が見つからなかったり、薬を飲んでも改善しない頭痛に悩んでいる方は、まずは歯科医院で相談してみましょう。
早期に対処することで、慢性化を防ぎ、快適な生活を取り戻せるかもしれません。
Oh my teethの無料診断で頭痛の原因を解消できるか確認してみよう
頭痛や顎の違和感が「噛み合わせの乱れ」からきているかどうか、自分では判断がつきにくいものです。
そんな方におすすめなのが、歯科矯正サービス「Oh my teeth(オーマイティース)」の無料矯正診断。「矯正が必要かわからないけど気になる」という方でも、気軽に相談できるのが魅力です。
また、診断後も原則オンラインで治療を進められるため、忙しい方でも矯正を始めやすい環境が整っています。
「頭痛の原因は噛み合わせかも?」と感じたら、まずは無料診断で確認してみてください。